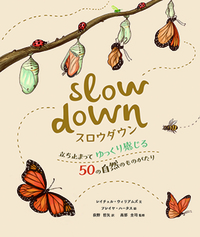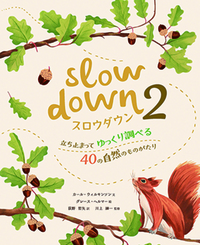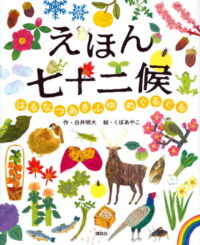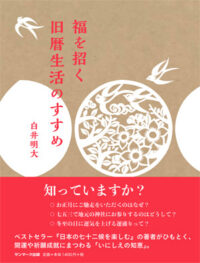一般カテゴリの記事一覧
秋の夜長、なにを読む?
2025年9月11日(木)|投稿者:kclスタッフ
こんにちは、たがねです。
9月に入りましたが、まだまだ暑い日が続いていますね。体感的には夏気分が抜けませんが、暦の上ではもう秋。期間限定メニューやスイーツで、一足先に秋を感じるようになりました。
9月の和風月名(旧暦での呼び名)である「長月」は「夜長月」から付けられたと言われています。秋分の日を過ぎたあたりから冬に向けて日照時間が短くなり、夜が少しずつ長く感じられるようになりますね。そんな夜が長い季節だからこそ、ゆったり過ごす時間が楽しみになります。
秋の夜長に楽しめることはいろいろありますが、図書館としてはやっぱり読書をおすすめしたいところ。
でも、いざ読書しようと思っても、読みたい本がなかなか見つからないことはありませんか? 気分を変えて、いつもは選ばないジャンルに挑戦してみたい時もありますよね。
今回は、秋の夜長のお供になる本選びに役立つ本をいくつかご紹介したいと思います。
まずはこちら、
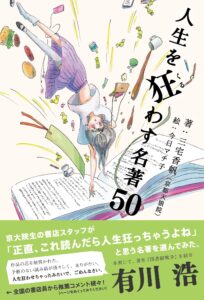
『人生を狂わす名著50』( 三宅 香帆/著 今日 マチ子/絵 ライツ社 2017.10)
新書大賞2025を受賞した『なぜ働いていると本が読めなくなるのか』が話題の三宅香帆さんによる書評集です。
本を読むことで考え方や生き方が大きく変わってしまうことを三宅さんは「人生を狂わす」と表現しています。
そんな人生を狂わす名著50冊を、気軽な語り口で紹介。まるで友達とおすすめ本を語り合うような軽やかな文体でスルスル読み進められます。さらに、各章の最後に「次に読みたい本」も3冊ずつ紹介してくれます。きっと気になる本が見つかると思います!
図書館には、この本以外にもいろんな書評集があります。書評の本は、請求記号019.9です。ぜひ手に取ってみてくださいね。
次に紹介するのはこちら、

『ブックデザイン365』( パイインターナショナル/編著 パイインターナショナル 2020.3)
本を選ぶ時、表紙に惹かれて思わず手に取ったことはありませんか? 表紙買いするという方も多いと思います。
この本は、文芸書から辞典までさまざまな本の、思わず手に取りたくなる装丁を365冊以上紹介しています。大きな写真とともに、書籍の概要やデザインコンセプトなどの情報がコンパクトにまとまっていて、眺めるだけで楽しい1冊です。ページをめくるたびに「こんな見せ方があるんだ!」と発見があり、本の楽しみ方がちょっと広がります。
この本の中で紹介されている本から気に入ったデザインの表紙を選んで読んでみるのも楽しそうですね。
図書館でも、新刊コーナーや展示棚、書架に表紙を見せて並べています。ぜひそちらにも注目してみてください。
最後に紹介するのはこちら、
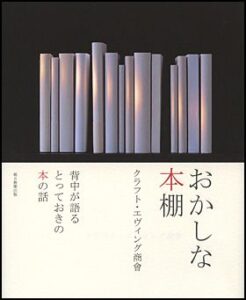
『おかしな本棚』( クラフト・エヴィング商會/著 朝日新聞出版 2011.4)
この本は、不思議な雰囲気が漂う本棚をテーマにした本です。「頭を真っ白にするための本棚」や「波打ち際の本棚」などのタイトルがついた本棚が写真とともに紹介されています。写真で見えるのは背表紙だけですが、眺めていると「どんな本なんだろう?」と想像が広がっていきます。紹介されている本棚には実在しない本も混じっていますが、ほとんどは実際にある本です。図書館で所蔵している本もあるので、探して読んでみてください。
図書館の本棚もずらっと並んだ背表紙を見ているとワクワクしますよね。
特に展示コーナーは定期的にテーマを入れ替えているので、期間限定の本棚が見られます。普段はあまり手に取らないジャンルの本とも出会えるかもしれません。ぜひチェックしてみてください。
そして、この図書館ブログでも本選びのお手伝いができるかもしれません。スタッフによるおすすめ本紹介の記事がたくさんあり、カテゴリー「おすすめ本」からまとめてご覧いただけます。過去の記事でもたくさんの本を紹介しているので、ぜひ参考にしてみてくださいね。
それでは、夜更かしはほどほどに!
秋の夜長に充実した読書時間を楽しんでくださいね。
<参考資料>
『なぜ働いていると本が読めなくなるのか』(三宅 香帆/著 集英社 2024.4)
『人生を狂わす名著50』(三宅 香帆/著,今日 マチ子/絵 ライツ社 2017.10)
『ブックデザイン365』(パイインターナショナル/編著 パイインターナショナル 2020.3)
『おかしな本棚』(クラフト・エヴィング商會/著 朝日新聞出版 2011.4)
<たがね>
疲れと悩みに寄り添う本
2025年5月6日(火)|投稿者:kclスタッフ
こんにちは、しちりです。
新年度が始まって1か月が経ちましたが、皆さまいかがお過ごしでしょうか?
新しい環境になる人もいれば、新しい人を迎え入れる人もいるかと思います。
中には、忙しく働き、疲れたり神経をすり減らす1か月を過ごした方もいるのではないでしょうか?
環境の変化で、疲れや悩みが出てくる時でもありますね。
今回は、そんな時に寄り添ってくれる本をご紹介したいと思います。
まず、1冊目はこちら。
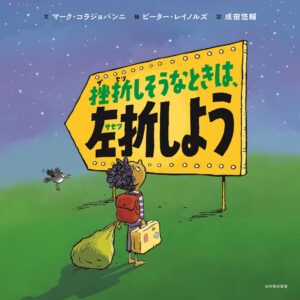
『挫折しそうなときは、左折しよう』 マーク・コラジョバンニ/文,ピーター・レイノルズ /絵,成田 悠輔/訳 光村教育図書 2023.5
だじゃれ? と思わず笑ってしまいそうな絵本ですが、不安に思っている時には逆にこの楽しい題名がいいのかもしれません。
誰でも挫折しそうな時はありますよね。これでいいのかな? また失敗しちゃうかな? 私たちは日々考えながら過ごし、決断しなくてはいけません。不安を感じる時もあると思います。
そんな時、どうすればいいのか?
そう、「左折する」のだそうです。
これだけだと??? と思うかもしれませんが、読んでいただければ、「左折する」とはどういうことなのかがよくわかります。
自分の気持ちの整理の仕方や前向きに考えるヒントが、わかりやすく描かれており、読んだ後には心がすーっと軽くなります。
「左折」の意味をかみしめることができます。
絵本ではありますが、大人でも充分に堪能できる内容です。親子で読んでも楽しめます。
経済学者で起業家の成田悠輔(なりた ゆうすけ)さんが、翻訳をされているのも注目です。
次はこちら。
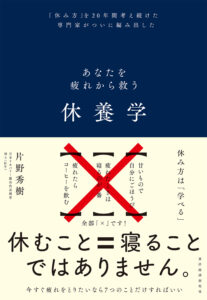
『休養学』 片野 秀樹/著 東洋経済新報社 2024.3
仕事、家事、育児、介護等、私たちは日々忙しく働いています。
疲れていてもやることがたくさんあって休めない。
休んでも疲れがうまくとれない。
そんな人もいるのではないでしょうか?
そんな方に読んでいただきたいのが、この本です。
休み方を20年間考え続けた著者が、「疲れとは何か」、「疲れているのに休まずにいるとどうなるのか」、「どんな休み方をすればよいのか」を解説してくれます。
だらだらと寝ているだけでは、疲れはとれません。
疲れのメカニズムと対処法を正しく理解することで、上手に疲労を回復し、自分に休養を与え、生活の質まで向上することができます。その秘訣がこの本には詰まっています。
身体だけでなく、考え方も前向きになる休養の方法で、毎日を生き生き過ごしてみませんか?
最後の1冊はこちらです。

『だれかに、話を聞いてもらったほうがいいんじゃない?』 ロリ・ゴットリーブ/著,栗木 さつき/訳 海と月社 2023.4
この作品は著者自らの経験を書き記したものです。彼女は、現役のセラピストであり、作家の仕事もこなすシングルマザー。
そのセラピストがセラピーに通うという、なんとも不思議な内容です。
彼女のところには、さまざまな人が患者としてやってきます。
暴言をはきまくるハリウッドのプロデューサー、結婚直後に癌で余命を宣告された女性、離婚歴のあるうつ病の女性等々。
彼女はセラピストとして、これらの患者に真正面から向き合い、信頼関係を築くために懸命に寄り添い、的確なアドバイスを繰り出します。
忙しいながらも充実した日々を送っていました。
ところが、つきあっていた彼氏が突然別れを宣告し、彼女のもとを去ってしまいます。
さあ大変。
友人に勧められ、セラピーを受けることになるのですが、いざ自分が患者の立場になると、ひたすら元カレを非難し続け、泣きわめき続ける…。
セラピストとしての、冷静で努力家の著者の姿はどこにいったの? と思うくらいの取り乱しようです。
彼女を担当した男性セラピストは、今までのセラピストの手法とはかなり違うやり方をする、変わった人物でした。そんな彼は、著者の真の悩みをズバリと言い当て、彼女をドキリとさせます。彼女は、反発しながらもセラピーに通うことになるのですが…。
セラピストとして患者と向き合い、一方で患者としてセラピストと対峙する彼女。一体どうなるのか、目が離せない展開に引き込まれます。
やがて、著者自身と彼女の患者たちが、それぞれ自分の悩みと向き合い乗り越えていく場面では、セラピストと患者の強い絆を感じることができ、感動で涙がとまりませんでした。
人は、深い悲しみや悩みを抱えていても、自分自身で再生することができる、そんな自信をつけさせてくれる本です。
今回は、3冊の本をご紹介しました。
疲れた時、不安になる時、あなたに寄り添い、あなたの心を癒してくれる本がきっとあると思います。
図書館でじっくりゆっくり本を読んでいただければ幸いです。
<紹介資料>
・『挫折しそうなときは、左折しよう』 マーク・コラジョバンニ/文,ピーター・レイノルズ /絵 成田 悠輔/訳 光村教育図書 2023.5
・『休養学』 片野 秀樹/著 東洋経済新報社 2024.3
・『だれかに、話を聞いてもらったほうがいいんじゃない?』 ロリ・ゴットリーブ/著,栗木 さつき/訳 海と月社 2023.4
<しちり>
ゆっくり、じっくり、あじわう秋
2024年9月9日(月)|投稿者:kclスタッフ
こんにちは、しちりです。
9月だというのに、まだまだ暑い日が続きますね。
夏休みも終わり、仕事に学校に忙しい毎日が戻ってきたかと思います。
最近は「タイパ(タイムパーフォンス)」に代表されるように、すべての物事を効率よく短時間でできることが、求められがち。
もちろん大切なことではありますが、タイパを求めるあまり、ふと窮屈さを感じてしまうのは、私だけでしょうか?
そこで今回は、少し立ち止まってゆっくりとした時間の中で、じっくりと味わうことのできる本をご紹介します。
こちらは、日々起こる自然の営みを、ゆっくりと味わうことのできる本です。
鳥、虫、動物の営みや自然の風景50項目を、各項目見開き2ページで説明しているのですが、物語のように流れる文章と、細部まで書き込まれた美しい絵に、たちまち心がひきこまれます。
ひとつひとつの出来事がきちんと理解できるとともに、じんわりと感動を覚える不思議さ。
毎日懸命に生きている生き物と、それを包み込む自然の美しさを感じて、心がほっとしてリラックスすることができます。
児童書ですが、大人でも十分に楽しめます。むしろ大人が読むと、子どもの頃の心象風景と重なり、懐かしく感じるかもしれません。
続編は、物語のような文章と、美しいイラストはそのままに、恐竜の化石ができる様子やブラックホールのことなど、時間も空間もスケールアップし、好奇心を大いにそそられます。
砂漠や氷山など、行ったことのない場所の話が出てきたかと思えば、ミミズや暗闇で光るネコの目の話などの身近な話があったりと、自然のさまざまな場面を感じることができるところが魅力です。
読みながら、「そうだったのか!」という気付きや、さらに詳しく調べてみたくなる内容も多く含まれています。
どちらの本も、2ページ完結なので、読みたいところだけを読んで楽しむこともできますが、あまりの魅力にページをめくる手が止まらないかもしれません。
旧暦を使用していた時代に日本人は、自然を敏感に感じ取り、季節ごとに名前をつけ、いにしえの知恵に学びながら、生活をしていました。
一年を二十四の季節にわけるのが二十四節気、それをさらに細かく分けたものを七十二侯と言うそうです。
この本では、リズミカルな詩の中に七十二候の季節の言葉を取り入れ、自然の移り変わりを楽しく分かりやすく表現しています。
ぜひ音読も楽しんでみて欲しい一冊です。
ひとつひとつは、ややわかりにくい言い回しもありますが、音読してみると、七十二候が詩のリズムの中に生き生きと表現されており、めぐる季節の美しさをすんなり味わうことができます。こんな季節の楽しみ方があったのかと思うほどです。
それにしても一年を七十二もの季節に分けると、一つあたりの季節は五日間ほど。昔の人が、たった五日でも季節の移ろいを感じていた、そのきめ細やかさを素晴らしいと感じずにはいられません。
旧暦に関連した本をもう一冊。
こちらの本では、明治の初めまで日本で使われていた旧暦の生活の知恵を、「福を招く」「恵みをいただく」「良縁を願う」など、七つのテーマにわけて紹介しながら、忙しく暮らしている今の私たちに、心のやすらぎ、体のいたわり方、幸せになるヒントを教えてくれています。
中には、春財布、土用の丑、七五三、冬至のゆず湯等など、今の日本人になじみのある習慣も多いのですが、改めて読んでみると、昔の人の、季節を感じながらしなやかに生き延びるための知恵がたくさん詰まっていて、自然とともに生きることの大切さを実感します。
その時々に気になったテーマを読んでも良いですし、最初から最後まで読み通すと、旧暦生活で培われた昔の人の英知に感嘆します。
そして最後の「おわりに」を読んでみてください。きっとその内容に、癒やしと納得を感じることができます。
忙しい毎日に疲れた時、是非読んでいただきたい本です。
最後にご紹介するのは、森林の植物のつながりについての大発見を記した本です。
お恥ずかしながら世界的ベストセラーということを知らなかった私ですが、それだけに衝撃の内容に圧倒されました。
森林の木々が、土中にある何層もの菌根ネットワークの複雑な働きによってつながり、支えあっていること。そして菌根ネットワークを使い、樹齢数百年にわたる大木(マザーツリー)が、驚きの役割をはたしていること。これらを著者は、30年以上にもわたる研究で発見したのでした。
研究の日々は、苦労の連続。途方もない時間と労力のかかる内容に驚くとともに、それでも森を守るために研究に没頭する姿に何度も心打たれました。
また、研究の内容だけでなく、家族との絆や辛い別れ、研究を批判する政府との軋轢、子育てと仕事の両立に悩む姿、新しい愛の形など、研究を取り巻く日常で起きる出来事が、ひとりの女性の視点でつぶさにつづられており、さまざまな立場の方に共感してもらえると感じました。
自然の壮大な支えあうシステムと、それを証明しようとする女性のひたむきさに、深く読めば読むほど、感動が増す本です。
皆さんも、毎日忙しく過ごしている中で、一呼吸おいて本を開いてみませんか?
夜が長くなってくる秋、本とともにゆったりとした時間を過ごしていただければ幸いです。
<参考資料>
『スロウダウン [1]』レイチェル・ウィリアムズ /文,フレイヤ・ハータス /絵,荻野 哲矢/ 訳 化学同人 2021.9
『スロウダウン 2』カール・ウィルキンソン/文,グレース・ヘルマー/絵, 荻野 哲矢/訳 化学同人 2021.9
『えほん七十二候』白井 明大/作,くぼ あやこ/絵 講談社 2016.3
『福を招く旧暦生活のすすめ』白井 明大/著 サンマーク出版 2017.12
『マザーツリー』スザンヌ・シマード/著,三木 直子/訳 ダイヤモンド社 2023.1
<しちり>
子どもって子どもって・・・
2024年5月6日(月)|投稿者:kclスタッフ
こんにちは、しちりです。
爽やかな5月となりました。
ゴールデンウィークにはこどもの日もあり、お子さんと楽しく過ごした方も多いのではないでしょうか?
しかし、子どもを育てるって、楽しいけれど本当に大変ですよね。
ということで今回は、子育てを題材に、大人も子どもも心がほぐれるような本をご紹介します。

『子どものことば』 (子どもとことば研究会/編・著 小学館 2017)
皆さんは、子どもの「ことば」にハッとすることはありませんか?
なんてするどい!なんてかわいい!そんな風に感じてるのか!
大人顔負けの表現に出会うこともあるはず。
この本では、主に幼稚園や保育園での日常で子どもたちが発した「ことば」を丁寧に取り上げています。
思わず笑ってしまう表現もたくさんあり、お子さんをお持ちの方やお子さんに関わるお仕事をされている方は、共感すること間違いなし!です。
また、それらの「ことば」から、子どもの発達や、どんな成長時期にあるのかを示して、周囲の大人はどのように寄り添えば良いのかをやさしく解説しています。
今しかないお子さんの「ことば」をたくさん書き留めておきたくなる本です。

『子どもをキッチンに入れよう!』(藤野 恵美/著 ポプラ社 2020)
「え?!子どもをキッチンに入れたら、危ないのでは?」
包丁や食器、洗剤、ガスの火など、キッチンは子どもがケガをする要素が満載なので、安全を第一に出入りをしないよう、柵をする方も多いのではないでしょうか。
しかし、この本の著者は、忙しい毎日でも、どうにか工夫をして家事と育児を楽しむために、子どもをキッチンに入れ、家事と育児を一緒にしてしまう、という決断をしたのでした。
これが、まさに、目からウロコ・・・。
十分に安全な環境に整えると、キッチンには色々な道具や食材があります。それらを上手に使いながら、親子でコミュニケーションを取り、楽しく作って、楽しく食べる!(各エピソードの終わりには、親子でできる料理のレシピ付き!)
食に興味がわけば、スーパーマーケットに行くことも楽しいイベントに!生産地の地名やお金の計算等、子どもが自然に楽しく学べる要素がいっぱい!
小説家でもある著者は、子育て本を1000冊ほど読み、子育てを分析した上で実践してみたというだけあって、取り入れたい点がたくさんあります。
忙しくても子育てを楽しむヒントがきっとあります。

『子どもが幸せになることば』(田中 茂樹/著 ダイヤモンド社 2019)
とは言うものの、子育てに不安や悩みはつきものですね。
子どもがだだをこねる、野菜を食べない、宿題をやらない、学校に行きたくない…。
私も散々悩ませられました。
この本では、そんな育児の悩みの場面を年齢ごとに分けて、声かけの言葉を具体的に示しながら、子も元気になり、親の気持ちもラクになる方法を紹介しています。
実際によくある場面を例に挙げ、「言いがちなことば」を「信じることば」に変えるだけ。
なんだ、これならすぐにでもできると思うものばかりです。困った場面に出会った時、子どもはどう感じ、何故困っているのかを分かりやすく説明しているので、親としてどう対応すれば良いのかが自然と理解できます。
著者は、20年間で5000以上の面接を行ってきたカウンセラーでもあり、やんちゃな4人のお子さんを育てた父親でもあり、毎週近所の小学生と小学校の体育館で遊びを通して関わってきた社会人でもあるという、さまざまな側面を持っています。
その著者の言葉には、優しさの中に経験に裏打ちされた重みがあります。
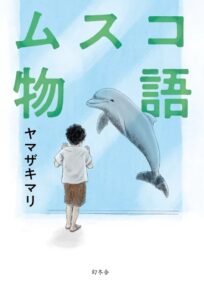
『ムスコ物語』(ヤマザキ マリ/著 幻冬舎 2021)
最後にご紹介したいのは、マンガ『テルマエ・ロマエ』の作者であり、文筆家のヤマザキマリさんの子育てを綴った本です。
イタリアでシングルマザーになる事を決意した著者は、日本に帰国後、仕事をいくつも掛け持ちしながら、全力で子育てをします。
その後イタリアの男性と結婚することになり、夫の仕事の都合でシリア→スペイン→アメリカと家族で移住することに。
異国の地で、お父さんとお母さんに振り回されっぱなしのムスコ君。苦労の連続にあいながらも、たくましく成長していく姿が印象的です。
どのエピソードも破天荒すぎて驚きの連続ですが、作者らしい歯に衣着せぬ言葉の中にも、ムスコ君への愛があふれています。
そして、本の最後には、ムスコ君からのメッセージつき。
作者に育てられた本人はどう思っていたのか、こちらもぜひ読んで頂きたいです。
子育てにまつわる本を紹介しました。
大人も子どもも元気になる本を読んで、子育てを楽しみたいですね。
《紹介資料》
『子どものことば』子どもとことば研究会/編・著 小学館 2017.8
『子どもをキッチンに入れよう!』藤野 恵美/著 ポプラ社 2020.11
『子どもが幸せになることば』 田中 茂樹/著 ダイヤモンド社 2019.2
『ムスコ物語』 ヤマザキ マリ/著 幻冬舎 2021.8
「もう一度、数学」の本
2023年4月4日(火)|投稿者:kclスタッフ
こんにちは。はじめまして「七里」と申します。
新年度がスタートしました。新生活を迎えた方、これから新しいことを始める方も多いのではないでしょうか?
そこで今回は、今まであまりご紹介できていなかった本を、心新たにご紹介しようと思います。
突然ですが、皆さんは数学がお好きですか?得意ですか?
残念ながら私は、「算数ならまだしも、難しい公式がオンパレードの数学なんて、社会に出たら使わないし、意味ないよね」と思っていました。
きっとこれからご紹介する本の著者からは、ガッカリな人間に認定されてしまうでしょう。
しかし、著者側も、私みたいな人間がいることは百も承知。
これからご紹介する本は、そんな人でも驚きと興味を持つことができ、数学(あるいは数学的思考)が世の中にどんな風に活用され、どれだけ重要なのかに力点を置いて書かれています。
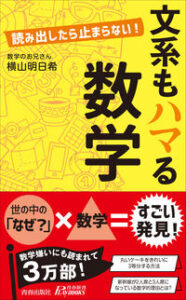
『文系もハマる数学』
横山 明日希/著 青春出版社 2020
三角ロボット掃除機のその三角の意味、コピー用紙サイズの半端な数字の謎、1ℓの牛乳パックの体積の不思議など、普段ちょっと気になっていたけれど、そこまで深く考えてなかった身近な内容から始まるこの本。
そうだったのか?!の連続で、すぐに引き込まれていきます。
そして、ニュースでよく見る社会問題の数学的解説や、人間関係の改善の方法など、今の生活で役に立つ内容ばかりで、一気に読みきることができました。

横山 明日希/著 講談社 2023
「数学、なかなかヤルじゃん」とここまでの私。いい気になって同じ著者の『はまると深い!数学クイズ』も読んでみました。
「数学は面白い」というしかけがさらにパワーアップしています。
また数学の歴史にも触れているので、先人たちの知恵を確かめることができます。
現在のデジタル時代に欠かせないAI。重要性は理解しているつもりでも、ついていくのはなかなか大変ですね。
そんな時に、デジタル時代の核となる数学の考え方の本はいかがでしょうか。
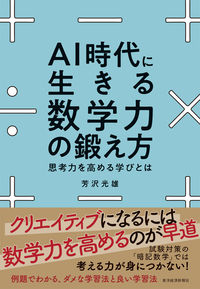
芳沢 光雄/著 東洋経済新報社 2020
この本は、本格的なAI時代を迎えた今、算数・数学教育を見直すことを訴えるために書かれた本です。
その根幹には、暗記数学がいかに日本の数学教育を衰退させたか、があります。
著者は暗記数学の弊害を、小学校の算数から中学・高校の数学に至るまで詳細に分析し、その上で、どうすればいいのかを丁寧に解説していきます。
最も心打たれた点は、著者が暗記数学の批判をただするのではないところです。
20年以上にわたり、大学生から講演先の小学生に至るまで、「考えて理解する」数学の大切さを地道に教え続け、それをこの本にまとめています。
そして、この数学の理解の仕方が、問題を解決する能力や社会を変えるひらめきに繋がっていくことを示してくれています。
内容には高校数学まで含まれているため、かなり難しい箇所もありますが、頭をフル回転して考えることができます。
家族を巻き込んで皆で考えてみるのも一考です。
学生や社会人の方はもちろんのこと、お子さんのいる方にも読んでらえると、これからの時代に必要な算数・数学の神髄が理解でき、教育にも活かせるかもしれません。
暗記数学だった私。数学なんて社会に出たら意味がないと言ってしまった私。
本当に著者に懺悔です。そしてこの本に感謝です。
こんな小説もありました。
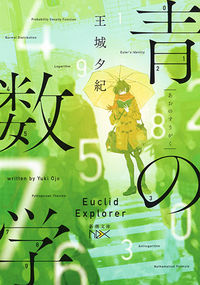
『青の数学 [1]』
王城 夕紀/著 新潮社 2016
「数学って何?」
主人公の高校生の栢山(かやま)は喫茶店で出会った女性の京(かなどめ)からこう聞かれ、答えに窮してしまいます。
そしてその答えを求めて、E²とよばれるネット上の数学の空間で、クセの強い高校生たちと切磋琢磨しながら、成長していく物語です。
それは、決して楽しいだけではなく、苦しくて長い道のり。
数学の沼にハマるとこんな心理状態が待っているのかと、つくづく感じさせる内容が胸を打ちます。
また、「数学とは何か」について、主人公と他の登場人物とのやり取りが、もはや禅問答のようで、哲学だと思わせる程です。
この本は、数学が好きな方や得意な方ほど、心情が痛いほどわかるかもしれません。
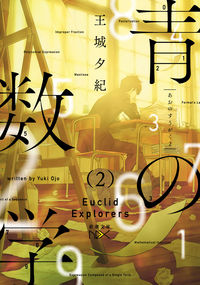
『青の数学2』
王城 夕紀/著 新潮社 2016
『青の数学2』では、『青の数学』で思わぬ展開のまま終わった続きを確認できます。
また、伏線の回収もあるので是非続けて読んで欲しい本です。
図書館には、他にもさまざまな数学の本を置いています。
数学が好きな方も、苦手な方も、もう一度手にとってみてはいかがでしょうか。
紹介資料
『文系もハマる数学』横山 明日希/著 青春出版社 2020
『はまると深い!数学クイズ』横山 明日希/著 講談社 2023
『AI時代に生きる数学力の鍛え方』芳沢 光雄/著 東洋経済新報社 2020
『青の数学 [1]』王城 夕紀/著 新潮社 2016
『青の数学2』王城 夕紀/著 新潮社 2016