児童カテゴリの記事一覧
第29回「図書館を使った調べる学習コンクール」の受賞作品
2026年1月15日(木)|投稿者:kclスタッフ
第29回「図書館を使った調べる学習コンクール」(公益財団法人 図書館振興財団)の 受賞作品が発表されました。
全国から12万点を超える作品が応募され、桑名市からは「第21回 桑名市図書館を使った調べる学習コンクール」で最優秀賞・優秀賞に選ばれた3作品が出品されました。
そして、気になる結果はこちら!
![]()
■優良賞(2作品)
・小学生の部(中学年)
「夜空の宝石箱~過去から未来へ~」
服部 永和さん(桑名市立長島北部小学校 4年)
・子どもと大人の部
「メダカの学校はどこにある?」
西田 紗季子さん(桑名市立在良小学校 1年)・西田 純さん(父)
■奨励賞(1作品)
・小学生の部(高学年)
「調べて広がる多肉植物ワールド」
平井 理菜さん(桑名市立大山田南小学校 6年)

受賞されたみなさん、おめでとうございます。
お子さん個人だけでなく、小学生以上のお子さんと一緒に大人の方でも応募できますので、みなさんが日常の中で興味・関心を持ったことをぜひ調べる学習コンクールの作品づくりに挑戦してみてください。
これからも、図書館は皆さんの調べる学習を応援・サポートいたします。
新年のごあいさつ 2026
2026年1月4日(日)|投稿者:kclスタッフ
あけましておめでとうございます
今年も桑名市立中央図書館とスタッフブログ「ブックとラック」を
よろしくお願いいたします
![]()
みなさま、お正月はいかがお過ごしでしょうか? 志るべです。
今年の干支は「午」ですね。今や、日々の暮らしの中で馬を目にする機会はなくなりましたが、かつて馬が身近にいた時代がありました。
江戸時代、桑名は東海道五十三次の内42番目の宿場町で、交通の要衝として重要な役目を担っていました。宿場には2つの役割がありました。ひとつは旅人に宿泊や休憩の場を提供する役割、もうひとつは人、物、情報を次の宿場へ運ぶ役割です。もちろん鉄道も車もありません。活躍したのが宿場に常備された「伝馬(てんま)」と呼ばれる馬でした。
公用の信書や荷物を人と馬が次の宿場まで運び、次々とリレー形式で目的地まで運ぶ制度を伝馬制度といいます。
慶長6年(1601)、「御伝馬之定」(『三重県史 資料編 近世4上』所収)が幕府から発布され、桑名宿には伝馬用の馬36疋(匹)を常備しておくことが定められました。そして、伝馬を利用するには「伝馬朱印状」(『三重県史 資料編 近世4上』所収)が必要でした。
馬だけでなく人も大活躍でした。その健脚ぶりには驚かされます。腹掛けに脚絆、はちまき巻いて飛脚箱をかついで走る姿、目に浮かびませんか? 大名や旗本から商人、名主、文人と利用層は拡大し、飛脚は次第にビジネス化していきます。御用(公用)荷物と町人荷物が同時に「公私混載」で運ばれていたといいます。
くわしくはこちら。
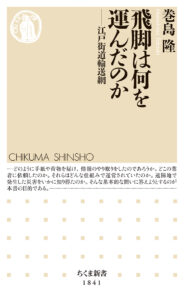
『飛脚は何を運んだのか』(巻島 隆/著 筑摩書房 2025.2)
『南総里見八犬伝』で有名な戯作者、曲亭(滝沢)馬琴の日記を読み解いて、飛脚について分析しています。馬琴は、江戸から伊勢国松坂(松阪市)に手紙を早便で、八日間を指定して出しています。早便は並便より短い規定日数(日限(ひぎり)という)で運ぶ特急便で、四日限(よっかぎり)、五日限、六日限などの日数設定がありました。手紙や原稿、資金や物資だけでなく各地の火災、地震、洪水といった情報も運ばれました。それによって人々は遠くで起きた災害の状況を知ることができたのです。
伝馬制度は、新政府が近代化を進める中、明治5年(1872)に廃止されました。
そんな頃、海外で人と馬はどういう関係にあったのでしょう?
明治10年(1877)、イギリスで『黒馬物語』という物語が発表されました。著者は、アンナ・スーウェル (Anna Sewell)、原題は「ブラックビューティ」(Black Beauty)。馬の視点で描かれた物語です。
『少年少女世界名作全集 6 黒馬物語』(ぎょうせい 1995.2)
著者は、子どもの頃のけががもとで一生足の痛みに苦しみ、『黒馬物語』を書いていた頃は外へ出ることもできなくなっていました。6年かけて作品を完成させ、出版の翌年に亡くなりました。生涯にこの作品1冊しか残していません。
訳者の足沢良子(たるさわ よしこ)さんが書かれた「解説」には、「彼女が生きた時代は、ビクトリア朝時代として、イギリスがもっとも富み栄えた時代でした。けれど富み栄えた都市の底辺には、ひどい貧困があったのです。(中略)彼女は作品の中で、その矛盾を、静かにけれど強く、馬という動物を通して訴えています」とあります。
また、馬について、「当時のイギリス人の生活には、なくてはならない動物でした。狩りや競馬のほかに、馬車というものが、現在の列車(当時、汽車はまだ、非常にぜいたくな乗り物でした)や車の役目を果たしていましたから」と書いています。
幼いころの黒馬ブラック・ビューティーは、牧場でかあさんと幸せに暮らしました。けれどその後、持ち主が次々と変わり、生活は一変します。つらい経験が描かれますが、著者の文章には馬への愛情、あたたかいまなざしが感じられます。
最後の1冊は、こちらの絵本。
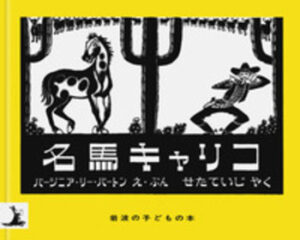
『名馬キャリコ』(バージニア・リー・バートン/え・ぶん,せた ていじ/やく 岩波書店 1979.11)
作者は、『ちいさいおうち』や『いたずらきかんしゃちゅうちゅう』でおなじみのバージニア・リー・バートン。
カウボーイのハンクと馬のキャリコが暮らすサボテン州は、どこにも囲いがなく、かぎがなく、牢屋がありません。それをいいことに、すごみやスチンカーと仲間たちは、牛どろぼうを企てます。さて、この悪漢どもをどうやって撃退するのか?
挿絵はモノクロで、見返しには写真のフィルムのようにすべての場面が順に載せられています。
最後のページは、みんなで新年を迎える場面で終わります。
かしこいキャリコのように、わたしたちも問題を解決していきたいものです。
どうぞ今年が平和な年でありますように。
![]()
<参考・紹介資料>
『日本交通史』(児玉 幸多/編 吉川弘文館 1992.11 )
『三重県史 資料編 近世4上』(三重県/編集 三重県 1998.3)
『飛脚は何を運んだのか』(巻島 隆/著 筑摩書房- 2025.2)
『少年少女世界名作全集 6 黒馬物語』(ぎょうせい 1995.2)
『名馬キャリコ』(バージニア・リー・バートン/え・ぶん,せた ていじ/やく 岩波書店 1979.11)
『ちいさいおうち』(バージニア・リー・バートン/文・絵,石井 桃子/訳 岩波書店 1991)
『いたずらきかんしゃちゅうちゅう』(バージニア・リー・バートン/ぶん え,むらおか はなこ/やく 福音館書店 1961.8)
<志るべ>
「第21回桑名市図書館を使った調べる学習コンクール」表彰式
2025年11月25日(火)|投稿者:kclスタッフ
2025年11月14日(金)に、第21回 桑名市図書館を使った調べる学習コンクールの表彰式が行われました。
今年は100作品のご応募いただきました。
![]()

![]()
そのうち、
☆最優秀賞 1作品
☆優秀賞 2作品(うち、子どもと大人の部1作品)
☆奨励賞 17作品(うち、子どもと大人の部1作品、地域賞3作品)
が入賞し、22名の方々が表彰されました。
今年度の受賞作品の一覧はこちらからご覧いただけます。
➡ 第21回 桑名市図書館を使った調べる学習コンクール入賞作品発表(PDF)
みなさんの疑問・興味を持ったことを一生懸命調べる姿がとても素敵でした。
これからも調査のお手伝いが出来るよう、図書館スタッフ一同サポートしてまいります。
最優秀賞・優秀賞に選ばれた作品は全国コンクールへ出品されます。
入賞作品の閲覧をご希望の方は、児童コーナー窓口へおたずねください。
疲れと悩みに寄り添う本
2025年5月6日(火)|投稿者:kclスタッフ
こんにちは、しちりです。
新年度が始まって1か月が経ちましたが、皆さまいかがお過ごしでしょうか?
新しい環境になる人もいれば、新しい人を迎え入れる人もいるかと思います。
中には、忙しく働き、疲れたり神経をすり減らす1か月を過ごした方もいるのではないでしょうか?
環境の変化で、疲れや悩みが出てくる時でもありますね。
今回は、そんな時に寄り添ってくれる本をご紹介したいと思います。
まず、1冊目はこちら。
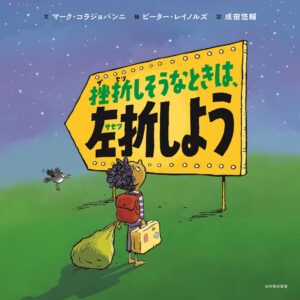
『挫折しそうなときは、左折しよう』 マーク・コラジョバンニ/文,ピーター・レイノルズ /絵,成田 悠輔/訳 光村教育図書 2023.5
だじゃれ? と思わず笑ってしまいそうな絵本ですが、不安に思っている時には逆にこの楽しい題名がいいのかもしれません。
誰でも挫折しそうな時はありますよね。これでいいのかな? また失敗しちゃうかな? 私たちは日々考えながら過ごし、決断しなくてはいけません。不安を感じる時もあると思います。
そんな時、どうすればいいのか?
そう、「左折する」のだそうです。
これだけだと??? と思うかもしれませんが、読んでいただければ、「左折する」とはどういうことなのかがよくわかります。
自分の気持ちの整理の仕方や前向きに考えるヒントが、わかりやすく描かれており、読んだ後には心がすーっと軽くなります。
「左折」の意味をかみしめることができます。
絵本ではありますが、大人でも充分に堪能できる内容です。親子で読んでも楽しめます。
経済学者で起業家の成田悠輔(なりた ゆうすけ)さんが、翻訳をされているのも注目です。
次はこちら。
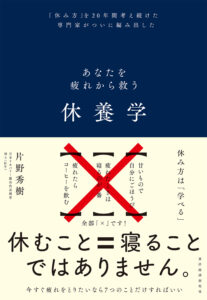
『休養学』 片野 秀樹/著 東洋経済新報社 2024.3
仕事、家事、育児、介護等、私たちは日々忙しく働いています。
疲れていてもやることがたくさんあって休めない。
休んでも疲れがうまくとれない。
そんな人もいるのではないでしょうか?
そんな方に読んでいただきたいのが、この本です。
休み方を20年間考え続けた著者が、「疲れとは何か」、「疲れているのに休まずにいるとどうなるのか」、「どんな休み方をすればよいのか」を解説してくれます。
だらだらと寝ているだけでは、疲れはとれません。
疲れのメカニズムと対処法を正しく理解することで、上手に疲労を回復し、自分に休養を与え、生活の質まで向上することができます。その秘訣がこの本には詰まっています。
身体だけでなく、考え方も前向きになる休養の方法で、毎日を生き生き過ごしてみませんか?
最後の1冊はこちらです。

『だれかに、話を聞いてもらったほうがいいんじゃない?』 ロリ・ゴットリーブ/著,栗木 さつき/訳 海と月社 2023.4
この作品は著者自らの経験を書き記したものです。彼女は、現役のセラピストであり、作家の仕事もこなすシングルマザー。
そのセラピストがセラピーに通うという、なんとも不思議な内容です。
彼女のところには、さまざまな人が患者としてやってきます。
暴言をはきまくるハリウッドのプロデューサー、結婚直後に癌で余命を宣告された女性、離婚歴のあるうつ病の女性等々。
彼女はセラピストとして、これらの患者に真正面から向き合い、信頼関係を築くために懸命に寄り添い、的確なアドバイスを繰り出します。
忙しいながらも充実した日々を送っていました。
ところが、つきあっていた彼氏が突然別れを宣告し、彼女のもとを去ってしまいます。
さあ大変。
友人に勧められ、セラピーを受けることになるのですが、いざ自分が患者の立場になると、ひたすら元カレを非難し続け、泣きわめき続ける…。
セラピストとしての、冷静で努力家の著者の姿はどこにいったの? と思うくらいの取り乱しようです。
彼女を担当した男性セラピストは、今までのセラピストの手法とはかなり違うやり方をする、変わった人物でした。そんな彼は、著者の真の悩みをズバリと言い当て、彼女をドキリとさせます。彼女は、反発しながらもセラピーに通うことになるのですが…。
セラピストとして患者と向き合い、一方で患者としてセラピストと対峙する彼女。一体どうなるのか、目が離せない展開に引き込まれます。
やがて、著者自身と彼女の患者たちが、それぞれ自分の悩みと向き合い乗り越えていく場面では、セラピストと患者の強い絆を感じることができ、感動で涙がとまりませんでした。
人は、深い悲しみや悩みを抱えていても、自分自身で再生することができる、そんな自信をつけさせてくれる本です。
今回は、3冊の本をご紹介しました。
疲れた時、不安になる時、あなたに寄り添い、あなたの心を癒してくれる本がきっとあると思います。
図書館でじっくりゆっくり本を読んでいただければ幸いです。
<紹介資料>
・『挫折しそうなときは、左折しよう』 マーク・コラジョバンニ/文,ピーター・レイノルズ /絵 成田 悠輔/訳 光村教育図書 2023.5
・『休養学』 片野 秀樹/著 東洋経済新報社 2024.3
・『だれかに、話を聞いてもらったほうがいいんじゃない?』 ロリ・ゴットリーブ/著,栗木 さつき/訳 海と月社 2023.4
<しちり>
第28回「図書館を使った調べる学習コンクール」の受賞作品
2025年1月16日(木)|投稿者:kclスタッフ
第28回「図書館を使った調べる学習コンクール」(公益財団法人 図書館振興財団)の 受賞作品が発表されました。
全国から12万点を超える作品が応募され、桑名市からは「第20回 桑名市図書館を使った調べる学習コンクール」で最優秀賞・優秀賞に選ばれた4作品が出品されました。
そして、気になる結果はこちら!
![]()
■優良賞(1作品)
・小学生の部(中学年)
「真夏のようかい大調査!!桑名・多度のようかい、ふしぎげんしょうをおえ!!」
米澤 慶さん(桑名市立多度中小学校 3年)
■奨励賞(2作品)
・小学生の部(中学年)
「わたしにもできることがある 小さな一歩 ~海や川の生き物を守るために~」
服部 永和さん(桑名市立長島北部小学校 3年)
・子どもと大人の部
「お金のはじまりと今」
山田 一輝さん(桑名市立伊曽島小学校 2年)・山田 理奈さん(母)
■佳作(1作品)
・小学生の部(高学年)
「いろのいろいろ」
平井 理菜さん(桑名市立大山田南小学校 5年)
![]()
受賞されたみなさん、おめでとうございます。
お子さん個人だけでなく、小学生以上のお子さんと一緒に大人の方でも応募できますので、みなさんが日常の中で興味・関心を持ったことをぜひ調べる学習コンクールの作品づくりに挑戦してみてください。
これからも、図書館は皆さんの調べる学習を応援・サポートいたします。



