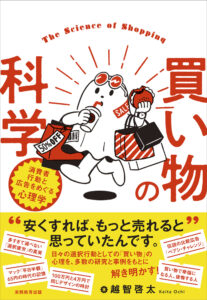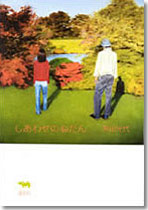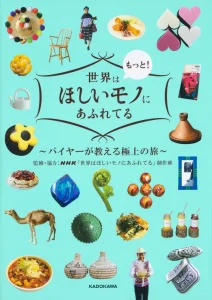2月に買いたいもの
2026年2月7日(土)|投稿者:kclスタッフ
こんちには、なばなです。
相変わらず寒い日が続いていますが、先日、寒さも吹き飛ぶような光景を目にしました。
百貨店の催事場を埋め尽くす人の波と、芸術品のようにきらびやかなチョコレート。
そう、バレンタイン催事場です。
メインであるチョコレートは、もちろん美味しそうでしたが…私の印象に残ったのは、催事場にいる人たちから感じる熱気でした。
「買えるだけ買いたい」とずらりと列をなす人々と、「全てを売りたい」とショーケースで構えるスタッフたち。
まるで合戦のような気迫を双方に感じました。平和な催事のはずなのですが…
「買いたい」「売りたい」という欲でここまで頑張り、その欲を満たして生き生きしている両者の姿に、「欲」も生きる力だと思い知らされました。
無欲は美徳だとよく言われますし、買い物しすぎるのはよくありません。
しかし、上手に自分の欲を満たす買い物ができたなら、日々の元気に繋がるかもしれません。
今回は、その参考になりそうな本を紹介したいと思います。
まず初めはこちらです。
自分の意志で欲しいものを選んだつもりでも、実は無意識に選ばされている。
そんな買い物を巡る行動と心理を、社会心理学を元にわかりやすく解説した本です。
安売りに潜む売れなくなるリスクや、ブランドの仕組みの分析なども載っていて、マーケティングの参考としても有用です。
どの話も最初は「そうなの!?」と驚いても、読み進めるうちに納得してしまいます。
面白いのは、買い物の心理学を学ぶことで、自分の買い物の傾向がわかってくること。
満足のいく買い物にするにはどうすればいいか、そのヒントが見えてきます。
買い物の雑学としても面白く、売る立場でも買う立場でも参考になる、さまざまな面からおすすめの本です。
続いてはこちらです。
直木賞作家である角田光代さんの買い物にまつわる思い出をまとめたエッセイ集です。
憧れた立ち食い蕎麦の値段、買い替えで悩むカバンの値段、行けなくなったメキシコ旅行の値段…
特別な買い物ではないのに、作者の独特の感性が絡んで、妙に面白く味わい深いエピソードになっています。
印象的なのは親子での温泉旅行の話。
先々で起きる失敗と、親子ならではの無神経さに笑いつつ、その時間の大切さが胸に沁みます。
最後の章の家計簿の話には、経験の価値を考えさせられました。
買って得られた体験が、自分の内面を作っていくなら、今の自分の中に何があるのか。
自分のための買い物を、改めて見つめ直したくなります。
鋭い視点で書かれた、ユーモアあふれる買い物エッセイです。
最後はこちらです。
トップバイヤー達の買い付けに同行したドキュメンタリーをまとめた本です。
世界中を飛び回るバイヤーたちは、モロッコ食器のために10時間もかけて山道を走り、また、オーガニックの知識を深めるため森に入ります。
中でもパワフルなのはチョコレートバイヤー。
日本未上陸のチョコレートを探して、オーストラリアから北欧まで世界中を飛び回って店巡り。
たどり着いた店では、一筋縄でいかないパティシエとの交渉が待っています。
まさに、心技体が求められるバイヤーの旅。
それでも、そこにしかない物に出会う度に、彼らは来てよかったと喜びます。
どの旅にも、かけた時間と努力、そしてバイヤーの信念が垣間見えます。
私たちが店先で何気なく見かける商品。
その中に彼らが見つけた「欲しいもの」があると思うと、景色が変わってくる気がします。
自分が夢中になれる、欲しいものを探しに行きたくなる本です。
満足できる買い物ができれば、それだけ楽しい時間が増えます。
図書館の本はそのヒントになるかもしれません。
図書館を通して、読書も買い物も楽しい時間にしませんか?
<参考資料>
『買い物の科学 消費者行動と広告をめぐる心理学 The Science of Shopping』(越智 啓太/著 実務教育出版 2024.8)
『しあわせのねだん』(角田 光代/著 晶文社 2005.5)
『世界はもっと!ほしいモノにあふれてる [1] バイヤーが教える極上の旅』 (NHK「世界はほしいモノにあふれてる」制作班/監修・協力 KADOKAWA 2020.4)
<なばな>
第29回「図書館を使った調べる学習コンクール」の受賞作品
2026年1月15日(木)|投稿者:kclスタッフ
第29回「図書館を使った調べる学習コンクール」(公益財団法人 図書館振興財団)の 受賞作品が発表されました。
全国から12万点を超える作品が応募され、桑名市からは「第21回 桑名市図書館を使った調べる学習コンクール」で最優秀賞・優秀賞に選ばれた3作品が出品されました。
そして、気になる結果はこちら!
![]()
■優良賞(2作品)
・小学生の部(中学年)
「夜空の宝石箱~過去から未来へ~」
服部 永和さん(桑名市立長島北部小学校 4年)
・子どもと大人の部
「メダカの学校はどこにある?」
西田 紗季子さん(桑名市立在良小学校 1年)・西田 純さん(父)
■奨励賞(1作品)
・小学生の部(高学年)
「調べて広がる多肉植物ワールド」
平井 理菜さん(桑名市立大山田南小学校 6年)

受賞されたみなさん、おめでとうございます。
お子さん個人だけでなく、小学生以上のお子さんと一緒に大人の方でも応募できますので、みなさんが日常の中で興味・関心を持ったことをぜひ調べる学習コンクールの作品づくりに挑戦してみてください。
これからも、図書館は皆さんの調べる学習を応援・サポートいたします。
新年のごあいさつ 2026
2026年1月4日(日)|投稿者:kclスタッフ
あけましておめでとうございます
今年も桑名市立中央図書館とスタッフブログ「ブックとラック」を
よろしくお願いいたします
![]()
みなさま、お正月はいかがお過ごしでしょうか? 志るべです。
今年の干支は「午」ですね。今や、日々の暮らしの中で馬を目にする機会はなくなりましたが、かつて馬が身近にいた時代がありました。
江戸時代、桑名は東海道五十三次の内42番目の宿場町で、交通の要衝として重要な役目を担っていました。宿場には2つの役割がありました。ひとつは旅人に宿泊や休憩の場を提供する役割、もうひとつは人、物、情報を次の宿場へ運ぶ役割です。もちろん鉄道も車もありません。活躍したのが宿場に常備された「伝馬(てんま)」と呼ばれる馬でした。
公用の信書や荷物を人と馬が次の宿場まで運び、次々とリレー形式で目的地まで運ぶ制度を伝馬制度といいます。
慶長6年(1601)、「御伝馬之定」(『三重県史 資料編 近世4上』所収)が幕府から発布され、桑名宿には伝馬用の馬36疋(匹)を常備しておくことが定められました。そして、伝馬を利用するには「伝馬朱印状」(『三重県史 資料編 近世4上』所収)が必要でした。
馬だけでなく人も大活躍でした。その健脚ぶりには驚かされます。腹掛けに脚絆、はちまき巻いて飛脚箱をかついで走る姿、目に浮かびませんか? 大名や旗本から商人、名主、文人と利用層は拡大し、飛脚は次第にビジネス化していきます。御用(公用)荷物と町人荷物が同時に「公私混載」で運ばれていたといいます。
くわしくはこちら。
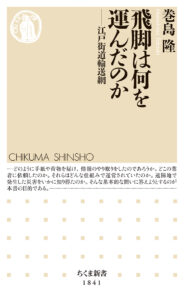
『飛脚は何を運んだのか』(巻島 隆/著 筑摩書房 2025.2)
『南総里見八犬伝』で有名な戯作者、曲亭(滝沢)馬琴の日記を読み解いて、飛脚について分析しています。馬琴は、江戸から伊勢国松坂(松阪市)に手紙を早便で、八日間を指定して出しています。早便は並便より短い規定日数(日限(ひぎり)という)で運ぶ特急便で、四日限(よっかぎり)、五日限、六日限などの日数設定がありました。手紙や原稿、資金や物資だけでなく各地の火災、地震、洪水といった情報も運ばれました。それによって人々は遠くで起きた災害の状況を知ることができたのです。
伝馬制度は、新政府が近代化を進める中、明治5年(1872)に廃止されました。
そんな頃、海外で人と馬はどういう関係にあったのでしょう?
明治10年(1877)、イギリスで『黒馬物語』という物語が発表されました。著者は、アンナ・スーウェル (Anna Sewell)、原題は「ブラックビューティ」(Black Beauty)。馬の視点で描かれた物語です。
『少年少女世界名作全集 6 黒馬物語』(ぎょうせい 1995.2)
著者は、子どもの頃のけががもとで一生足の痛みに苦しみ、『黒馬物語』を書いていた頃は外へ出ることもできなくなっていました。6年かけて作品を完成させ、出版の翌年に亡くなりました。生涯にこの作品1冊しか残していません。
訳者の足沢良子(たるさわ よしこ)さんが書かれた「解説」には、「彼女が生きた時代は、ビクトリア朝時代として、イギリスがもっとも富み栄えた時代でした。けれど富み栄えた都市の底辺には、ひどい貧困があったのです。(中略)彼女は作品の中で、その矛盾を、静かにけれど強く、馬という動物を通して訴えています」とあります。
また、馬について、「当時のイギリス人の生活には、なくてはならない動物でした。狩りや競馬のほかに、馬車というものが、現在の列車(当時、汽車はまだ、非常にぜいたくな乗り物でした)や車の役目を果たしていましたから」と書いています。
幼いころの黒馬ブラック・ビューティーは、牧場でかあさんと幸せに暮らしました。けれどその後、持ち主が次々と変わり、生活は一変します。つらい経験が描かれますが、著者の文章には馬への愛情、あたたかいまなざしが感じられます。
最後の1冊は、こちらの絵本。
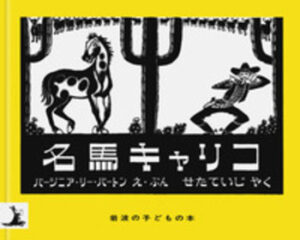
『名馬キャリコ』(バージニア・リー・バートン/え・ぶん,せた ていじ/やく 岩波書店 1979.11)
作者は、『ちいさいおうち』や『いたずらきかんしゃちゅうちゅう』でおなじみのバージニア・リー・バートン。
カウボーイのハンクと馬のキャリコが暮らすサボテン州は、どこにも囲いがなく、かぎがなく、牢屋がありません。それをいいことに、すごみやスチンカーと仲間たちは、牛どろぼうを企てます。さて、この悪漢どもをどうやって撃退するのか?
挿絵はモノクロで、見返しには写真のフィルムのようにすべての場面が順に載せられています。
最後のページは、みんなで新年を迎える場面で終わります。
かしこいキャリコのように、わたしたちも問題を解決していきたいものです。
どうぞ今年が平和な年でありますように。
![]()
<参考・紹介資料>
『日本交通史』(児玉 幸多/編 吉川弘文館 1992.11 )
『三重県史 資料編 近世4上』(三重県/編集 三重県 1998.3)
『飛脚は何を運んだのか』(巻島 隆/著 筑摩書房- 2025.2)
『少年少女世界名作全集 6 黒馬物語』(ぎょうせい 1995.2)
『名馬キャリコ』(バージニア・リー・バートン/え・ぶん,せた ていじ/やく 岩波書店 1979.11)
『ちいさいおうち』(バージニア・リー・バートン/文・絵,石井 桃子/訳 岩波書店 1991)
『いたずらきかんしゃちゅうちゅう』(バージニア・リー・バートン/ぶん え,むらおか はなこ/やく 福音館書店 1961.8)
<志るべ>
読んで味わう旅の時間
2025年12月9日(火)|投稿者:kclスタッフ
こんにちは、たがねです。
12月に入り、外に出るのがちょっと億劫になる季節になってきました。遠出をするのは大変だけど、旅気分は味わいたい…そんなときにピッタリなのが旅行エッセイです。ページをめくるだけで知らない風景に出会えたり、誰かの視点を借りてちょっとそこまで気分を味わえたり。エッセイを読んで次に行きたい場所を見つけるのも楽しいですよね。
今回は、気軽に読めて思わずどこかへ出かけたくなるような、旅エッセイをいくつかご紹介します。
まずはこちら、
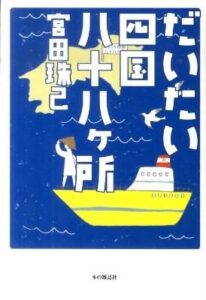
『だいたい四国八十八ケ所』(宮田 珠己/著 本の雑誌社 2011.1)
お遍路といえば「厳かな巡礼の旅」というイメージがありますが、旅行エッセイストの宮田珠己さんは「一周してみたい、全部回ってみたい、いっぱい歩きたい」という理由でお遍路の旅に出ます。四国八十八ヶ所をめぐりながら出会う風景の観察や人々へのツッコミが軽快につづられています。旅の途中、自転車でしまなみ海道を渡ったり、カヌーで四万十川を下ったりと寄り道もあり最後まで飽きずに楽しく読めます。足にできたマメとの戦いや、単調な道への愚痴など思わず笑ってしまう場面もたっぷり。お遍路の基礎知識も自然と頭に入るので、旅の案内書としてもエッセイとしても楽しめる1冊です。
次に紹介するのはこちら、
『死ぬまでに行きたい海』(岸本 佐知子/著 スイッチ・パブリッシング 2020.12』
著者は翻訳家・岸本佐知子さん。岸本さんが気の向くままに出かけて、見聞きしたことを綴ったエッセイ22編が収録されています。
タイトルには「海」とありますが、海へ行ったことを書いたエッセイではありません。海外の話もありますが、岸本さんが出不精なため基本的には家から近い東京近郊に行った話が多いです。近所の景色も岸本さんが見るとどこか新鮮で、読みながら「そんなところに目を向けるんだ!」とクスっとしてしまいます。旅らしい大きな事件は起きないけれど、小さな発見や思い出話がじんわり楽しい1冊です。文の途中に挿し込まれている写真は岸本さん自身がスマートフォンで撮ったものだそうです。文章の雰囲気にぴったりの味のある写真を見るのも楽しいと思います。
静かな語り口の不思議な余韻が残る文章で、年末のあわただしい時間の合間に読むと、気持ちが落ち着きそうです。
最後に紹介するのはこちら、
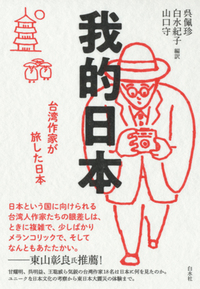
『我的日本』(呉 佩珍/編訳,白水 紀子/編訳,山口 守/編訳 白水社 2019.1)
日本を旅した時、外国の人はどんなところに心を動かされているんだろう? そんな素朴な疑問にこたえてくれるのが、この1冊です。台湾の作家18人が、それぞれの視点で日本各地を旅して出会った風景や人、ちょっとした驚きや違和感まで、瑞々しい語り口で綴っています。お花見や大阪弁などふだん見慣れた日本の文化も、海外の作家の目を通すとまったく違って見えるのが面白いところ。日本人にとってあたりまえの文化が外からはどう見えるのか、読んでいると新鮮な気持ちになります。いつもの日本を別の国の人が旅する日本として楽しめる旅エッセイ集です。
旅の本を読むと、いつも見ている風景が少し違って見えるかもしれません。そんな視点の変化も旅エッセイの楽しさのひとつ。
図書館では他にも旅行エッセイを所蔵しているので、気になる1冊を手に取って、旅行気分を味わってみてくださいね。
<参考資料>
『だいたい四国八十八ケ所』(宮田 珠己/著 本の雑誌社 2011.1)
『死ぬまでに行きたい海』(岸本 佐知子/著 スイッチ・パブリッシング 2020.12)
『我的日本』(呉 佩珍/編訳,白水 紀子/編訳,山口 守/編訳 白水社 2019.1)
<たがね>
年末年始の休館と貸出延長のお知らせ
2025年11月27日(木)|投稿者:kclスタッフ
「ブックとラック」をご覧のみなさま、こんにちは。
桑名市立中央図書館の年末年始休館と、貸出期間延長のご案内です。
中央図書館では以下の期間が休館となります。
【休館期間】
12月28日(日)~1月3日(土)
※休館期間中の返却はくわなメディアライヴ1階の返却ポストをご利用ください。
ただし、CD、DVD、大型絵本・大型紙芝居、ゆめはま文庫、桑名市外から取り寄せた図書は破損のおそれがありますので、開館日にカウンターへお持ちください。
また、休館に伴い貸出期間の延長を行います。
【図書・雑誌の貸出期間延長】
12月14日(日)~12月27日(土)の貸出 …3週間
※桑名市外から取り寄せた図書は、貸出期間が異なります
【CD・DVDの貸出期間延長】
12月21日(日)~12月27日(土)の貸出 …2週間
通常よりも一週間長く借りられるとあって、毎年たくさんの資料が貸出されます。
この機会に、なかなか手を出せずにいた本にチャレンジしてみるのはいかがでしょうか?
館内にはテーマに沿った資料を集めた特集コーナーがございます。
何を読もうか迷った時は、ぜひ特集コーナーもご覧ください。
今年も図書館をご利用いただき、ありがとうございました。
2026年も桑名市立中央図書館をご利用・ご活用いただきますようよろしくお願い申し上げます。
よいお年をお迎えください。