妖刀村正と呼ばれる理由
2025年4月8日(火)|投稿者:kclスタッフ
こんにちは、なばなです。
史上二度目の大阪万博の開催が目前に迫ってきました。
今回の万博では関西パビリオンの三重県ブースで、なんと、桑名宗社に奉納されている村正の太刀が展示されるそうです。
桑名宗社の村正が選出されるとは…
驚きですが、桑名市民にとっては喜ばしいことですね。
村正を鍛刀した千子村正は、桑名で活躍した刀匠でした。 そして、千子村正の刀派は千子派と呼ばれ、代々村正の名を継ぎ、優れた刀をいくつも作りました。
今回展示されるのは、二代目村正が制作した二振りの太刀です。
それぞれに「勢州桑名郡益田庄藤原朝臣村正作/天文十二天癸卯五月日」と銘があり、一方の鎬地(しのぎじ)には「春日大明神」、もう一方には「三崎大明神」と刻まれています。
この二振りは第二次世界大戦の時、当時の宮司により刀身を保護するために漆が塗られました。
長年そのままでしたが、令和元年(2019)に「春日大明神」の一振りが研磨され、本来の美しい刀身を取り戻しました。
今回、この「春日大明神」の太刀が展示され、もう一振りの「三崎大明神」の太刀も研磨・修復後に展示される予定です。
全国的に「名刀村正」として知られている村正ですが、もう一つ別の呼称があります。
それは「妖刀村正」です。
なぜ、 村正の刀が「妖刀」と呼ばれるようになったのか。
それは、村正が、徳川家康の祖父、父、妻といった一族の死因、負傷の原因となり、さらには家康自身が、村正によって負傷したという逸話があるからです。
これにより村正は、将軍徳川家に禍をもたらす「妖刀」とされました。
けれども客観的に見て、この話は正しいといえるのでしょうか?

『村正 伊勢桑名の刀工 刃文にやどる「妖刀」の虚と実』(桑名市博物館/編集 桑名市博物館 2016.9)
こちらは桑名市博物館の特別企画展の図録です。
逸話の元になった事件は、『徳川実紀』(歴代将軍の事歴を叙述した史書)に記録があるものの、使われた刀については不明瞭な点もあり、すべての刀が村正だったかは断言できない、とあります。
『三重県刀工・金工銘鑑』には、徳川家の本拠地である岡崎は桑名に比較的近く、よく切れると評判の村正の刀は、広く岡崎の武士の手に渡っていたため、村正による事件も多かったのではないか、と述べられています。
岡崎の武士を率いる立場の徳川家は、特に村正で怪我をしやすい環境にあったと考えられますね。
その結果、家康は村正に対して、次々に一族を傷つける不吉さを感じたのかもしれません。
つまり、岡崎の武士に人気があったばかりに、徳川一族に禍をもたらす刀と言われるようになったわけで...
村正、とばっちりでは…? と言いたくなりますね。
さらに『村正 伊勢桑名の刀工 刃文にやどる「妖刀」の虚と実』には、『徳川実紀』の記録を見ると村正の刀を忌むことが、幕府内の慣習として定着していたとみて間違いない、と記されています。
いずれにせよ、幕府に村正の刀を不吉とする見方は浸透していったようです。
また、時が経つにつれ、村正の逸話は変化していきました。
徳川家にとって不吉な刀から、徳川家に限らず怪我をさせる刀へと変わっていったのです。
江戸の世間話を書き溜めた随筆集「耳嚢(みみぶくろ)」(南町奉行・根岸 鎮衛[ねぎし・しずもり]/著)には、当時の村正の逸話があり、その変化が確認できます。(『日本庶民生活史料集成 第16巻 奇談・紀聞』収録)
その上、追い打ちをかけるように、戯曲や芝居などの創作物で、村正が凶器として取り上げられました。
村正、とばっちり、再び…
村正の刀による悲劇を演じた「大願成就殿下茶屋聚(たいがんじょうじゅてんがちゃやむら)」や「八幡祭小望月賑(はちまんまつりよみやのにぎわい)」などの歌舞伎が続々と登場しました。
歌舞伎は当時は大人気でしたので、妖刀村正が世間に広まるのも早かったのでしょう。
手にするのもためらわれる村正ですが、むしろ「徳川家に忌避された刀」であることが好まれ、幕末には討幕派の武士が村正を求めるということもあったようです。
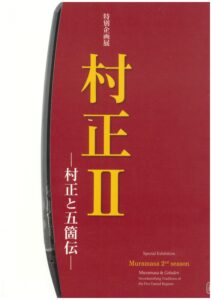
『特別企画展 村正Ⅱ 村正と五箇伝』(桑名市博物館/編集 桑名市博物館 2018.10)
こちらには、官軍の中心人物の有栖川宮熾仁親王(ありすがわのみや・たるひとしんのう)、三条実美や西郷隆盛などが村正を所持していたとあります。
村正にすれば「そんな験担ぎされても…」という思いかもしれませんが。
こうして現在に至るまで妖刀の逸話が広まってしまった村正ですが、刀自体はどの時代においても高く評価されました。
徳川幕府に仕えながらも、その実用性と美しさに魅了されて密かに所持していた武士も少なくありませんでした。
忌避されていたはずなのに、徳川家所蔵の刀の中にも村正は残っています。
「名刀」故に「妖刀」と呼ばれるようになり、「妖刀」と呼ばれてもなお求められた村正の刀。
だからこそ、その魅力は「妖刀」と呼ばれるのにふさわしい気もします。
大阪万博に行かれる際は、ぜひ立ち寄ってみてはいかがでしょうか。
<参考資料>
『三重県刀工・金工銘鑑』(田畑 徳鴦/著 三重県郷土資料刊行会 1989)
『村正 伊勢桑名の刀工 刃文にやどる「妖刀」の虚と実』(桑名市博物館/編集 桑名市博物館 2016.9)
『特別企画展 村正Ⅱ 村正と五箇伝』(桑名市博物館/編集 桑名市博物館 2018.10)
『桑名の伝説・昔話』(近藤 杢/編,平岡 潤/編 桑名市教育委員会 1965)
『日本名刀物語』(佐藤 寒山/著 白凰社 1962.6)
『日本刀名工伝』(福永 酔剣/著 雄山閣 2022.2)
『日本刀工刀銘大鑑』(飯田 一雄/著 淡交社 2016.3)
『日本刀の教科書』(渡邉 妙子/共著,住 麻紀/共著 東京堂出版 2014.10)
『刀剣画報 村正・蜻蛉切と伊勢桑名の刀』(ホビージャパン 2023.12)
『日本庶民生活史料集成 第16巻 奇談・紀聞』(谷川 健一/編集委員代表 三一書房 1970.10)
<なばな>




コメントを残す