"有名人"を含む 3件の記事がヒットしました。
第三弾 桑名ゆかりの有名人
2023年10月21日(土)|投稿者:kclスタッフ
こんにちは、志るべです。
秋も深まってまいりましたが、みなさまいかがお過ごしでしょうか。
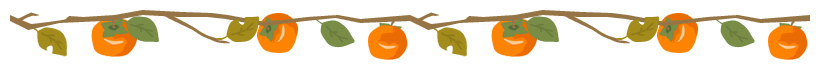
前回のブログ「遠くて近い留学の話」で、なばなが海外留学の本を紹介しました。
その中で「昔は海外留学したと聞くと、自分とは別世界の話のように感じた」と書いていますが、今から155年ほど前、時は明治維新、まさしく別世界に飛び込んだ若者たちがいました。
その一人が、駒井重格(こまい しげただ)です。
今回は、「第三弾 桑名ゆかりの有名人」として駒井重格を紹介したいと思います。
駒井重格は幕末の桑名藩士で、維新後にアメリカに留学し、後に専修学校(現在の専修大学)を創設した人物です。
駒井家は代々、久松松平家(徳川家康の異父弟の家系。「第二弾 桑名ゆかりの人物」をご覧ください)に仕えた家柄で、学者をたくさん輩出しています。
重格の父、祖父は共に儒学者で、重格は14歳という若さで家督を継ぎました。
戊辰戦争では神風隊に所属して戦っています。
桑名藩は庄内(山形県)で降伏しますが、重格は寒河江の激戦で負傷していたこともあり、鶴岡城下に近い大山で謹慎し、その後、帰藩しました。
明治7年(1874)、旧桑名藩主・松平定教(まつだいら さだのり)のお供をする形でアメリカへ留学し、ニュージャージー州にあるラトガース大学で経済学を学びました。
この留学中、後に専修学校を創設する仲間、相馬永胤(そうま ながたね)、田尻稲次郎(たじり いなじろう)、目賀田種太郎(めがた たねたろう)と出会います。
相馬と田尻は嘉永3年(1850)生れで、目賀田と駒井は、その3年後、黒船が来航した嘉永6年(1853)に生れました。(『専修大学 105年』では重格は嘉永5年(1852)生れ、とあります)
幕末には、相馬(彦根藩)と田尻(薩摩藩)は倒幕派、目賀田(幕臣)と駒井(桑名藩)は佐幕派と敵対する立場にありました。
そんな彼らを描いた小説がこちら、
『蒼翼の獅子たち』(志茂田 景樹/著 河出書房新社 2008.10)
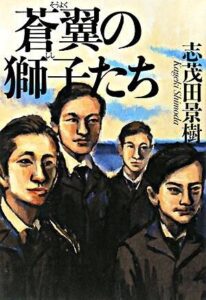
『蒼翼の獅子たち』(志茂田 景樹/著 河出書房新社 2008.10)
物語は、明治3年(1870)9月28日、17歳を迎えたばかりの目賀田種太郎がアメリカ留学に出発するところから始まります。
幕末の動乱を生き抜いて留学を果たした若者たちは、しだいに新しい学校を創ることに情熱を傾けていきます。
彼らが目指したのは、日本語で法律学と経済学を学ぶことができる専門学校を創ることでした。
帰国後の明治13年(1880)、現在の専修大学の前身である専修学校を設立します。
専修大学の創設についてくわしく記されている一冊はこちら、
『専修大学 105年』(専修大学出版局 1984.9)
建学の精神の項では、重格たち4人がどのように生き、専修学校設立に至ったかが記されています。
こちらもご覧ください。
『専修大学史紀要 創刊号』(専修大学大学史資料課 2009.3)
専修大学長の日高義博氏が「建学の精神と大学の未来」として、4人の創立者について語っています。
『専修大学史紀要 第11号』(専修大学大学史資料室 2019.3)
専修大学の歴史が記されています。
その後、重格は大蔵省、農商務省の官僚として近代国家の土台づくりに力をそそぎます。
東京大学予備門や岡山中学校(現在の岡山県立岡山朝日高等学校)、岡山県師範学校(現在の岡山大学)等で英語、経済学を教え、教育者としても活躍しました。
また語学に堪能であった重格は、フランス経済学を日本に導入し、多くの著作・翻訳書を残しています。
明治32年(1899)には、高等商業学校(現在の一橋大学)の校長に就任し、専攻部を2年延長、商業学士号を新設する等、学校改革に着手しました。
けれども、在任中の明治34年(1901)12月9日に急逝しました。享年48歳でした。
桑名藩士であった駒井家の歴史については、こちら、
『美術館紀要 第1号』(桑名市立文化美術館 1979.7)
西羽晃氏が「駒井重格について」と題して考察しています。
また、『郷土史を訪ねて』(西羽 晃/著 朝日新聞社名古屋本社 2010.6)の中にも駒井重格についてまとめられています。
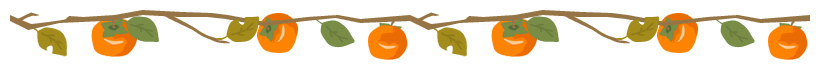
幕末から明治へと大きく変化した時代を生き抜いた若者たち。
どのような思いを抱いて海を渡り、そこで何を見て、何を感じ、どう行動したのでしょう。
図書館の本を通して彼らの姿に触れてみませんか?
<紹介資料>
『蒼翼の獅子たち』 志茂田 景樹/著 河出書房新社 2008.10 AL936シモ
『専修大学 105年』 専修大学出版局 1984.9 L289コ桑名人物
『専修大学史紀要 創刊号』 専修大学大学史資料課 2009.3 L289コ桑名人物
『専修大学史紀要 第11号』 専修大学大学史資料室 2019.3 L289コ桑名人物
『美術館紀要 第1号』 桑名市立文化美術館 1979.7 L069ク
『郷土史を訪ねて』 西羽 晃/著 朝日新聞社名古屋本社 2010.6 AL292ニ
<志るべ>
第二弾 桑名ゆかりの有名人
2023年6月16日(金)|投稿者:kclスタッフ
こんにちは、「志るべ」です。
梅雨入りを迎える季節となりましたが、みなさまいかがお過ごしでしょうか。
早いもので、今年も半分が過ぎようとしています。
![]()
2月の、かぶらの記事「桑名ゆかりの有名人」お読みいただけましたか?
大河ドラマでも活躍する三人、本多忠勝、服部半蔵、千姫をご紹介しました。
ドラマは着々と進み、忠勝は常に家康の側に仕え、半蔵は御用とあらばどこからともなく風のように現れます。
忠勝は、鹿角の冑を身に着けて立派な槍「蜻蛉切(とんぼきり)」を持った、いかつい武将のイメージが強いですが、ドラマの中ではまっすぐで初々しい、若き姿が印象的です。
忍者として知られる半蔵は、自分は武士であって忍者とは呼ばれたくないというちょっと屈折した部分を持って描かれています 。
家康の孫娘、千姫は現時点では登場していません(まだ生まれていませんね)
![]()
今回は第二弾としてさらに、家康に関係する「桑名ゆかりの有名人」をご紹介します。
まず、桑名藩主、久松松平定勝とその家系。
家康の実母、於大の方は初め松平広忠に嫁ぎ、家康を生みます。
ところが実家の水野家(兄の水野信元)が今川家(嫁ぎ先である松平家の主君)から織田方についたため、離縁となりました。
その後、於大の方は久松俊勝に再嫁し、生まれた男子の一人が定勝でした。定勝は家康の異父弟であることから松平姓を許され、本多家が姫路へ移封となった後、桑名藩主となりました。
定勝の後はその子、定行が継ぎ、定行が伊予国松山藩(現在の愛媛県松山市)へ移封すると定行の弟、定綱が藩主として桑名に入ります。
この定綱の家系が桑名の久松松平家で、幕末に京都所司代を務めた桑名藩主、定敬(会津藩主松平容保の実弟)へとつながっていきます。
久松松平家は越後高田藩(現在の新潟県上越市)、陸奥国白河藩(現在の福島県白河市)と一旦桑名を離れます。白河藩時代には、寛政の改革に取り組んだ老中松平定信を藩主としています。
その後、文政6年(1823)の国替えで再び桑名へ戻り、この地で幕末を迎えました。
そのため久松松平家の史料は桑名に残されています。
桑名の人々から「鎭國さん」として親しまれている鎭國守國神社には、鎭國公(定綱)と守國公(定信)が祀られています。
また、鎭國守國神社の楽翁公百年祭記念寶物館には数々の久松松平家に関する史料が収められています。中には、国の重要文化財「集古十種板木」(松平定信の命により、全国の神社仏閣や諸家に伝わる名品を模写蒐集し編集したもの)もあります。
収蔵品は、
『桑名松平伝来資料史料調査報告書 鎮國守國神社所蔵資料目録』(桑名市教育委員会 2004.3)
にまとめられています。
また、桑名市立中央図書館では久松松平家の家譜を所蔵しています。
デジタル化した家譜はこちらをご覧ください。
『御家譜 全』
![]()
次は、桑名藩主、奥平松平忠雅とその家系。
すでにドラマに登場している、家康の長女亀姫(母は正室瀬名、築山殿)は奥平信昌に嫁ぎ、忠明を生みます。家康の娘と結婚したことから、奥平家も松平姓を許されました。
久松松平家(定綱の家系)が高田へ移封になると、忠雅(忠明の子である忠弘の孫)が藩主として桑名へ入りました。
文政6年(1823)に久松松平家が桑名へ戻ると、奥平松平家は武蔵国忍藩(現在の埼玉県行田市)へ移り、忍で幕末を迎えました。
そのため奥平松平家の史料は行田市に残されています。
『松平家四百年の歩み 長篠城より忍城へ』
奥平松平家の歴史をじっくりと辿ることができます。

『松平家四百年の歩み 長篠城より忍城へ』(大沢 俊吉/著 講談社・音羽サービスセンター(製作) 1970)
![]()
それにしても久松家や奥平家だけでなく、家康を中心に親戚関係でつながる家と人、複雑すぎます。
それぞれの家や人にさまざまな思いや野望があって・・・
家康はこれら膨大な親戚関係をすべて把握していたのでしょうか。
本やドラマに登場する人物は、描かれ方によってずいぶん印象が異なります。
本当はどんな人たちだったのでしょう?
元々、人はいろんな側面を持ち合わせているということでしょうか。
いずれにしても今とは異なる時代を生きた人たち、現代の尺度で測るのは難しいかもしれませんね。
図書館の資料を通して家康の時代、当時の桑名、そしてそこに生きた人々に思いを馳せてみませんか?
![]()
<紹介資料>
『桑名松平伝来資料史料調査報告書 鎮國守國神社所蔵資料目録』 桑名市教育委員会 2004.3 AL/025/ク/
『御家譜』 L/AKI/ROM/0300
『松平家四百年の歩み 長篠城より忍城へ』大沢 俊吉/著 講談社・音羽サービスセンター(製作) 1970 L/205/オ/江戸
<志るべ>
桑名ゆかりの有名人
2023年2月14日(火)|投稿者:kclスタッフ
こんにちは、かぶらです。
近頃、テレビ番組や新聞などで桑名ゆかりの人物が取り上げられているのをよく目にします。
やはり、大河ドラマの影響って凄いんだなぁと驚く毎日です。
ところで、今回の大河ドラマでも活躍する「桑名ゆかりの人物」に、どんな人がいるかはご存じでしょうか?
よくは知らないけれど、名前は聞いた事がある!というあの人やこの人も、実は桑名にゆかりがあるのです。
大河ドラマをきっかけに戦国時代に興味を持たれた方も。歴史の本は何だか難しそうだから…とこれまで避けていた方も。
どなたでも手に取りやすく、わかりやすい作品を今回はご紹介いたします。
まずは、徳川家康を支え、「戦国最強」ともいわれた徳川四天王・本多忠勝。

柿安コミュニティパーク(吉之丸コミュニティパーク)に銅像が建っているので、ご存じの方も多いのではないでしょうか?
小牧長久手の戦いや、小田原攻めなど数々の合戦でその豪勇を賞賛された忠勝。
慶長5年(1600)関ヶ原の戦いでまた大功を立て、慶長6年(1601)4月24日、桑名藩初代藩主として桑名へ入りました。
忠勝は「慶長の町割」といわれる大規模な町の整備を行い、今も町割りの名残が随所に見られます。
「慶長の町割」の様子は、船馬町で酒屋を営んでいた太田吉清が当時の出来事を記した『慶長自記』に残されています。
『慶長自記』については、過去のブログでご紹介していますのでご覧ください。
「『慶長自記』から見る桑名」(2017.7.11公開)
慶長15年(1610)10月18日に63歳で亡くなった忠勝は、桑名の浄土寺に葬られました。
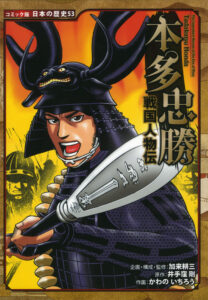
『本多忠勝 コミック版日本の歴史 53』
(加来 耕三/企画・構成・監修,井手窪 剛/原作,かわの いちろう/作画 ポプラ社 2016年刊)
忠勝が用いた武器として有名な「蜻蛉切」などの三名槍や、“徳川に仇なす”といわれた「村正」について解説された本。
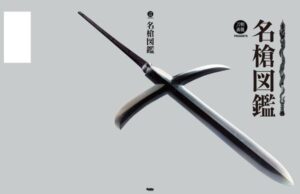
『名槍図鑑』
(ホビージャパン 2021年刊)
![]()
二人目は、徳川家康の危機を救った人物として名高い、服部半蔵です。
天正10年(1582)6月2日、京都本能寺で織田信長が明智光秀に討たれた時、家康は堺にいました。
身の危険を感じた家康は、わずかな家臣を連れて伊賀を抜け三河の国へ帰ります。
この時、地元の土豪を説得し、警固に付けて無事に伊賀を抜けさせたのが、先祖の出自が伊賀である服部半蔵正成でした。
その後、遠江国に八千石を賜り、関東入国後に伊賀同心200人を預けられました。
服部石見守正成が正式な名乗りで、慶長6年(1601)に亡くなります。
正成の子、正就が父の跡を継ぎ、八千石の内の三千石を弟の正重に分け与えられました。
後に正成の子孫達は桑名藩の家老職となり、「半蔵」の名乗りは正重の家が継ぎました。
幕末、正重の家系の正義が桑名藩の家老を勤めました。
彼は21歳の時に家老となり、京都所司代として京都にいる藩主・松平定敬を支えます。
正義の実弟は同じく家老の酒井孫八郎で、幕末の桑名藩は彼らの奔走により再興されました。
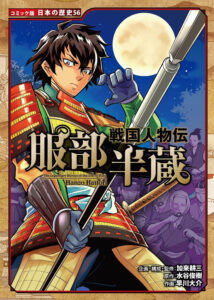
『服部半蔵 コミック版日本の歴史 56』
(加来 耕三/企画・構成・監修,水谷 俊樹/原作,早川 大介/作画 ポプラ社 2017年刊)
虚実混在の人物の墓から架空の主人公など、全国各地にある不思議な墓や意外な墓を紹介。
東京にある服部半蔵正成の墓や、皇居の半蔵門についても取り上げられています。
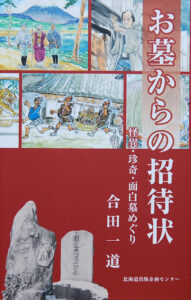
『お墓からの招待状』
(合田 一道/著 北海道出版企画センター 2017年刊)
![]()
最後は、徳川家康の孫・千姫です。
千姫は慶長2年(1597)、京都伏見で生まれました。
父親は徳川2代将軍・秀忠、母親はNHK大河ドラマ「江~姫たちの戦国~」のヒロイン・江。
母方の祖父は浅井長政、祖母は織田信長の妹・お市の方です。
慶長8年(1603)千姫は、母方のいとこにあたる豊臣秀頼に嫁ぎます。千姫わずか7歳、秀頼11歳の政略結婚でした。
元和元年(1615)、大坂夏の陣で大坂城は落城し、義母・淀殿と秀頼は自害します。
千姫は家康の命により落城前に助け出されました。
助け出された千姫は江戸に戻る途中で桑名に立ち寄っています。
この時の桑名城主が、本多忠勝の嫡男・忠政です。
桑名から熱田へ向かう千姫の旅の供を務め、七里の船旅を指揮したのが、忠政の嫡男・忠刻でした。
忠刻は美男な上、剣の名手でもあり、この道中で千姫が忠刻を見初めたといわれています。
江戸に戻った千姫は祖父・家康に、忠刻に嫁ぎたいと申し出ました。こうして二人の結婚が実現。
この時、千姫の化粧料(持参金)として員弁郡八田郷一万石と鉱山が桑名藩領になりました。
元和3年(1617)に国替えで本多家が姫路に移るまでの10カ月、二人は桑名で新婚生活を過ごしました。
千姫が奉納したといわれる祖父・家康の木像が、今も春日神社に残されています。
忠勝が桑名で行った慶長の町割りの様子や、大坂城を脱出した千姫が忠刻と出会う様子などがマンガでわかりやすく描かれている作品。
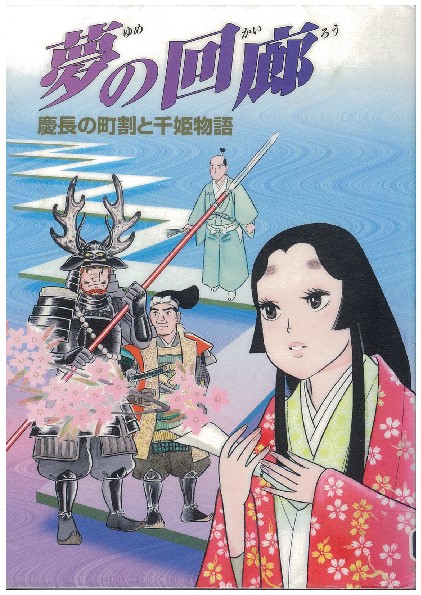
『夢の回廊 慶長の町割と千姫物語』
(古城 武司/漫画 2001年刊)
時代に翻弄されながらも、凛として生きた千姫の生涯を描いた小説。
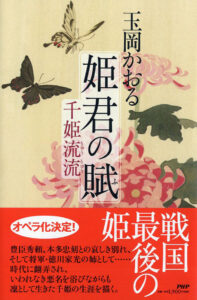
『姫君の賦』
(玉岡 かおる/著 PHP研究所 2018年刊)
いかがでしたでしょうか?
今回ご紹介した本は、ごく一部のものです。
忠勝や半蔵、千姫についてもっと知りたい!と思われた方は、ぜひ中央図書館で本を探してみてください。
桑名や三重県に関する本は、4階の「桑名・三重コーナー」や「歴史の蔵」にございます。
子どもさんにも読みやすい本は、3階の「YL 子どものための郷土資料」にご用意しています。
希望の本が見つけられない時は、いつでも図書館スタッフにお尋ねください。
<かぶら>



