#kclスタッフおすすめ本 『硝子戸の中』
2023年3月3日(金)|投稿者:kclスタッフ
【 繰り返し読む 】

『硝子戸の中』
(夏目 漱石/著 岩波書店 2008年刊)
『吾輩は猫である』『坊つちゃん』『こゝろ』など、誰もが一度は目に耳にした事のある作品を残した夏目漱石。
その中でも特に、私がつい何度も繰り返し読んでしまう作品が、今回ご紹介する『硝子戸の中』です。
小説?いいえ、こちらは今の時代でいうところの“エッセイ”にあたります。
『硝子戸の内』は、『東京朝日新聞』と『大阪朝日新聞』で大正4年(1915)1月13日から2月23日まで掲載されました。(※休載3回を含む、全39回)
掲載が始まる前年の暮れに風邪を引き、硝子戸の中で座ったり寝たりしてその日を過ごしていた漱石。
そんな彼のもとへ、硝子戸の中へ、時々入ってくる人々がいます。
今作は、そんな人々とのやり取りや、漱石自身が思い巡らせた事が書かれた作品です。
明治38年(1905)に『吾輩は猫である』。
明治39年(1906)に『坊つちゃん』。
そして今作の前年、大正3年(1914)に『こゝろ』を発表し、新聞に何かひとつ書けば「政治家や軍人や実業家や相撲狂を押し退けて書く事になる」漱石。
そんな彼のもとを訪れる人々というのは、さぞ名のある、または真面目で難しい話を持ち込むのだろう。
と思い読み進めば、嘘でしょう?と思わず呟いてしまう人物が現れる。
漱石の頭を巡る事柄も、幼い頃友人に二十五銭うっかり騙し取られた話など、自身の過去を脈絡なくつらつらと書いていく。
「ただ春に何か書いてみろといわれたから、自分以外にあまり関係のない詰らぬ事を書くのである。」
と冒頭でことわっている通り、これは本当に彼以外には関係のない事ばかりでした。
けれど、「自己を語ることに寡黙」であったはずの漱石が、自身の記憶を振り返り、家族や現在の自分の心境を書いている。
読み終えてみれば、漱石という人物に対して親しみを覚えてしまう。
何故繰り返し読みたくなるのか、については私自身も正直なところよくわかりません。
何か読もうかな、と自宅の本棚を眺めた時、つい手を伸ばしてしまうのが『硝子戸の中』なのです。
余談ですが、作品タイトル『硝子戸の中』の「中」は何と読むと思いますか?
「うち」「なか」と本文中で漱石自身も双方使っているため、タイトルは何と読むのが正しいのかしら、と思い耽る事があります。
ワイド版岩波文庫解説の竹盛さんの解釈が私は好きなのですが、皆さんはどうでしょう?
▼本の貸出状況は、こちらから確認いただけます
『硝子戸の中』
▼出版社/書影画像元
岩波書店
※次回更新は2023年3月17日(金)の予定です
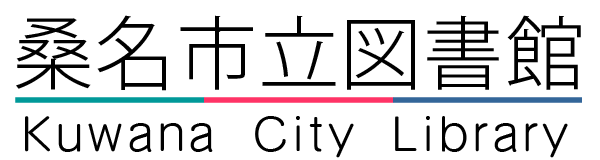



コメントを残す