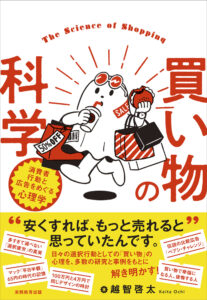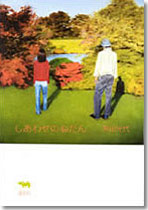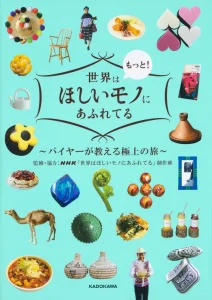ブログの記事一覧
博物館×中央図書館 令和7年度ML連携セミナー(第6弾)「刀剣眩耀展のたのしみ方」を開催します!
2026年2月10日(火)|投稿者:kclスタッフ
ML連携とは、博物館(Museum)と図書館(Library)が連携し、共通のテーマに沿って企画展示やセミナーを開催する協力活動です。
中央図書館では、博物館展示のテーマに合わせた関連書籍の展示や、博物館職員等によるセミナーを行います。
クリックするとPDFが開きます
第6弾は博物館春季企画展「刀剣眩耀-甦る桑名宗社の村正-」の開催に合わせて、関連書籍展示と桑名市博物館職員によるセミナー「刀剣眩耀展のたのしみ方」を行います。
<セミナー紹介>
桑名市博物館春季企画展「刀剣眩耀(げんよう)―甦る桑名宗社の村正―」では、漆が研がれた三重県指定文化財《太刀 銘 村正》(桑名宗社蔵)を展観するとともに、桑名宗社に伝わるご宝物を展示いたします。
セミナーでは、村正をはじめ、展示作品の見どころをご紹介いたします。
※状況により変更・中止となる場合がございます。予めご了承いただきますようお願いいたします。
<日程>
博物館×中央図書館 令和7年度ML連携企画 セミナー「刀剣眩耀展のたのしみ方」
講師:桑名市博物館 小関 明里 氏
日時:3月15日(日) 午後1時30分から午後3時
場所:くわなメディアライヴ 2階
参加費:200円 ※おつりのないようご用意ください
定員:50名(先着順、事前申込制)※定員になり次第締め切ります
申込み方法:直接窓口、または電話で中央図書館へ
申込み開始:2月19日(木)午前11時~ ※受付は各日午後5時まで
問い合わせ:桑名市立中央図書館 〒511-0068 桑名市中央町三丁目79 0594-22-0562
2月に買いたいもの
2026年2月7日(土)|投稿者:kclスタッフ
こんちには、なばなです。
相変わらず寒い日が続いていますが、先日、寒さも吹き飛ぶような光景を目にしました。
百貨店の催事場を埋め尽くす人の波と、芸術品のようにきらびやかなチョコレート。
そう、バレンタイン催事場です。
メインであるチョコレートは、もちろん美味しそうでしたが…私の印象に残ったのは、催事場にいる人たちから感じる熱気でした。
「買えるだけ買いたい」とずらりと列をなす人々と、「全てを売りたい」とショーケースで構えるスタッフたち。
まるで合戦のような気迫を双方に感じました。平和な催事のはずなのですが…
「買いたい」「売りたい」という欲でここまで頑張り、その欲を満たして生き生きしている両者の姿に、「欲」も生きる力だと思い知らされました。
無欲は美徳だとよく言われますし、買い物しすぎるのはよくありません。
しかし、上手に自分の欲を満たす買い物ができたなら、日々の元気に繋がるかもしれません。
今回は、その参考になりそうな本を紹介したいと思います。
まず初めはこちらです。
自分の意志で欲しいものを選んだつもりでも、実は無意識に選ばされている。
そんな買い物を巡る行動と心理を、社会心理学を元にわかりやすく解説した本です。
安売りに潜む売れなくなるリスクや、ブランドの仕組みの分析なども載っていて、マーケティングの参考としても有用です。
どの話も最初は「そうなの!?」と驚いても、読み進めるうちに納得してしまいます。
面白いのは、買い物の心理学を学ぶことで、自分の買い物の傾向がわかってくること。
満足のいく買い物にするにはどうすればいいか、そのヒントが見えてきます。
買い物の雑学としても面白く、売る立場でも買う立場でも参考になる、さまざまな面からおすすめの本です。
続いてはこちらです。
直木賞作家である角田光代さんの買い物にまつわる思い出をまとめたエッセイ集です。
憧れた立ち食い蕎麦の値段、買い替えで悩むカバンの値段、行けなくなったメキシコ旅行の値段…
特別な買い物ではないのに、作者の独特の感性が絡んで、妙に面白く味わい深いエピソードになっています。
印象的なのは親子での温泉旅行の話。
先々で起きる失敗と、親子ならではの無神経さに笑いつつ、その時間の大切さが胸に沁みます。
最後の章の家計簿の話には、経験の価値を考えさせられました。
買って得られた体験が、自分の内面を作っていくなら、今の自分の中に何があるのか。
自分のための買い物を、改めて見つめ直したくなります。
鋭い視点で書かれた、ユーモアあふれる買い物エッセイです。
最後はこちらです。
トップバイヤー達の買い付けに同行したドキュメンタリーをまとめた本です。
世界中を飛び回るバイヤーたちは、モロッコ食器のために10時間もかけて山道を走り、また、オーガニックの知識を深めるため森に入ります。
中でもパワフルなのはチョコレートバイヤー。
日本未上陸のチョコレートを探して、オーストラリアから北欧まで世界中を飛び回って店巡り。
たどり着いた店では、一筋縄でいかないパティシエとの交渉が待っています。
まさに、心技体が求められるバイヤーの旅。
それでも、そこにしかない物に出会う度に、彼らは来てよかったと喜びます。
どの旅にも、かけた時間と努力、そしてバイヤーの信念が垣間見えます。
私たちが店先で何気なく見かける商品。
その中に彼らが見つけた「欲しいもの」があると思うと、景色が変わってくる気がします。
自分が夢中になれる、欲しいものを探しに行きたくなる本です。
満足できる買い物ができれば、それだけ楽しい時間が増えます。
図書館の本はそのヒントになるかもしれません。
図書館を通して、読書も買い物も楽しい時間にしませんか?
<参考資料>
『買い物の科学 消費者行動と広告をめぐる心理学 The Science of Shopping』(越智 啓太/著 実務教育出版 2024.8)
『しあわせのねだん』(角田 光代/著 晶文社 2005.5)
『世界はもっと!ほしいモノにあふれてる [1] バイヤーが教える極上の旅』 (NHK「世界はほしいモノにあふれてる」制作班/監修・協力 KADOKAWA 2020.4)
<なばな>
ブックリサイクルを開催します
2026年2月1日(日)|投稿者:kclスタッフ
ブックリサイクルでは、保存期限を過ぎた雑誌などをお持ち帰りいただけます。

日時:2026年3月7日(土) 9:00~15:00
場所:くわなメディアライヴ2階 第1会議室
入場無料
事前申込不要
※持ち帰り用の袋等は、各自でご持参ください
※より多くの方に配布するため、お1人様10冊までのお持ち帰りでお願いいたします
詳しくは、当日の会場にてご確認ください。
駐車場の数に限りがありますので、来館の際には公共交通機関のご利用をお勧めします。
満車の場合は柿安シティホール(市民会館)の立体駐車場または、
桑名市パブリックセンターの駐車場をご利用ください。
「こばとお正月スペシャル2026」を開催しました
2026年1月23日(金)|投稿者:kclスタッフ
2026年1月12日(月・祝)、桑名市立中央図書館おはなし室にて「こばとお正月スペシャル2026」を開催いたしました。
今回のおはなし会では、お正月にちなんだお話や、今年の干支の「午(うま)」が登場する絵本を読み聞かせしました。
おはなし室の座るスペースがなくなるほど、とてもたくさんの方に参加していただき、大いに盛り上がりました。
![]()
『ぴかぴかのおてがみ』(乾 栄里子/作,たしろ ちさと/絵)は、大晦日に謎のお手紙が届くおはなしです。誰からのお手紙なのか、みんな予想しながら終始楽しそうに聞いていただけました。

紙芝居『きんいろのうま』(おかもと あつし/脚本,伊藤 秀男/絵)は、金色の馬、銀色の馬、鉛色の馬の3頭の馬が登場する、今年にぴったりの昔話です。

最後に「ゆらゆらだるま」と「ブンブンごま」を作りました。

だるまには表情を、ブンブンごまにはデザインを自由に描いてもらいました。
みなさん、とても上手でした!


ご参加していただいた方だけでなく、私たちスタッフもとても楽しい時間を過ごすことができました。
ありがとうございました。
![]()
今後も皆様に楽しんでいただけるイベントをおこなっていきたいと思います。
これからのイベント情報もお楽しみに♪
X(旧Twitter)でもイベント情報を発信していますので、ぜひチェックしてください。
第29回「図書館を使った調べる学習コンクール」の受賞作品
2026年1月15日(木)|投稿者:kclスタッフ
第29回「図書館を使った調べる学習コンクール」(公益財団法人 図書館振興財団)の 受賞作品が発表されました。
全国から12万点を超える作品が応募され、桑名市からは「第21回 桑名市図書館を使った調べる学習コンクール」で最優秀賞・優秀賞に選ばれた3作品が出品されました。
そして、気になる結果はこちら!
![]()
■優良賞(2作品)
・小学生の部(中学年)
「夜空の宝石箱~過去から未来へ~」
服部 永和さん(桑名市立長島北部小学校 4年)
・子どもと大人の部
「メダカの学校はどこにある?」
西田 紗季子さん(桑名市立在良小学校 1年)・西田 純さん(父)
■奨励賞(1作品)
・小学生の部(高学年)
「調べて広がる多肉植物ワールド」
平井 理菜さん(桑名市立大山田南小学校 6年)

受賞されたみなさん、おめでとうございます。
お子さん個人だけでなく、小学生以上のお子さんと一緒に大人の方でも応募できますので、みなさんが日常の中で興味・関心を持ったことをぜひ調べる学習コンクールの作品づくりに挑戦してみてください。
これからも、図書館は皆さんの調べる学習を応援・サポートいたします。


-212x300.jpg)