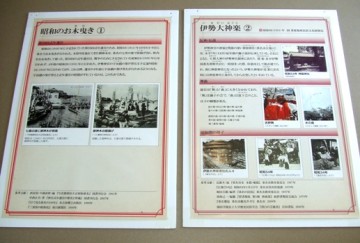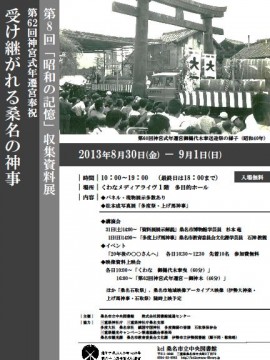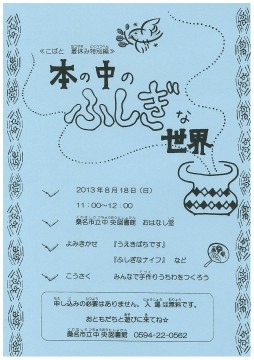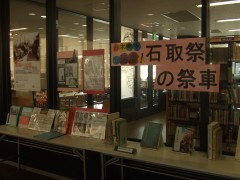ブログの記事一覧
ここに注目!「昭和の記憶」直前レポート
2013年8月19日(月)|投稿者:kclスタッフ
8月30日(金)~9月1日(日)の
桑名市立中央図書館の一大イベント
第8回「昭和の記憶」収集資料展の開催が
いよいよ近づいてまいりました!
今年のテーマは
昭和期の神事の様子を伝える写真やパネル、
貴重な現物資料の展示のほか、
桑名市の学芸員による講演、映像資料の上映、
お子様も楽しめるクイズラリーやすごろくコーナーなど
盛りだくさんのプログラムをご用意しております。
私<ぐりこ>の注目ポイントは、次の3つ!
◆その1 華やかな現物資料や懐かしの昭和の写真
「昭和の記憶」は、市民の方や関係機関にご協力いただき、
図書に限らない多様な資料を収集する事業。
収集資料展では、普段の図書館では見ることのできない
現物資料や珍しい写真なども多数展示します。
今回はテーマが“神事”ということで、
みなさまからご提供いただく資料も
華やかで賑やかなものが多いのが特徴。
特に、多度大社の上げ馬神事に関しては、
神事に奉仕する自治会(御厨/みくりや)の皆様からご協力をいただき、
上げ馬の騎手の雅な花笠やブチ(鞭)といった
たいへん貴重な実物の装具をお借りして展示します。
◆その2 「昭和の記憶」特別講演
今回の資料展では、2つの講演会を予定しています。
① 31日(土)14:00~ 「資料展展示解説」
桑名市博物館学芸員の方による展示資料の解説講演。
実際の展示物を見ながらその説明を聞くことができる、
「昭和の記憶」収集資料展ならではのチャンスです!
② 1日(日)14:00~ 「多度上げ馬神事」
桑名市教育委員会文化課学芸員の方による講演。
多度大社の上げ馬神事は、約700年も受け継がれている
伝統の行事。また、多度大社は「北伊勢神宮」とも称され、
伊勢神宮との関わりが深い古社です。
煌びやかな現物資料や多数の写真・映像資料とともに、
歴史ある神事の勇壮な世界に触れてみませんか?
◆その3 映像資料上映会
各日10:00~ 「くわな 御樋代木奉曳 (60分)」
14:00~ 「第62回神宮式年遷宮―御神木 (46分)」
式年遷宮にまつわる行事は、20年に1度だけ。
「お木曳きは観たことがない」という方もいらっしゃるのでは
ないでしょうか? (実は私<ぐりこ>もその一人です)
映像資料では、
そんな神事の盛大な様子を知ることができます。
上記2本のほかにも、「桑名石取祭」のDVD、
(伊勢大神楽・上げ馬神事・石取祭に関する映像)なども
随時上映します。ぜひお楽しみください。
桑名市にお住まい方はもちろん、市外にお住まいの方にも
お楽しみいただける資料展になると思います!
ご来場、心よりお待ちしております。
========================
第8回「昭和の記憶」収集資料展
第62回神宮式年遷宮奉祝 受け継がれる桑名の神事
|会期| 8月30日(金)~9月1日(日)
|時間| 10:00~19:00(最終日は18:00まで)
|場所| くわなメディアライヴ1階 多目的ホール
|主催|
桑名市立中央図書館 株式会社図書館流通センター
|協力|
三重県神社庁 三重県神社庁桑名支部
多度大社 桑名宗社 鎮国守国神社
多度御厨の皆様 石取祭保存会
三重県観光キャンペーン推進協議会事務局
桑名市観光課 桑名市教育委員会文化課
伊勢市立伊勢図書館
(順不同 敬称略)
<ぐりこ>
図書館へGO!! 夏休み後半のイベント情報
2013年8月15日(木)|投稿者:kclスタッフ
体温を越える猛烈な暑さが
続いていますね。
さて、今回のブログでは、8月後半の
桑名市立中央図書館イベント情報を2つお届けします!
①★こばと『おはなし会 夏休み特別編』
「本の中のふしぎな世界」
とき:8月18日(日) 11:00~
場所:中央図書館おはなし室(はまぐりの部屋)
申込不要・入場無料
年齢制限はありません。
なんともふしぎな絵本の読み聞かせや、
呪文のようなことば遊び、連日の暑さを吹き飛ばすような、
自分だけのオリジナルうちわづくりをおこないます。
本の中のふしぎな世界を、みんなで一緒に
体験してみませんか?
②★「昭和の記憶」収集資料展
前回のブログでもお伝えした
桑名市立中央図書館の一大イベント
「昭和の記憶」収集資料展のうち、
お楽しみイベントのお知らせです。
8月30日(金)~9月1日(日)の3日間、
くわなメディアライヴ1階多目的ホールにて開催される
第8回「昭和の記憶」収集資料展。
謎解きが楽しめる”クイズラリー”や
お伊勢参りのバーチャル体験が出来る!?
また、【20年後の○○さんへ】と題した
プログラムもご用意しております。
今から20年後のあなたは何才でしょうか?
どんな人になっているのでしょう?
この機会に、20年後の自分に、あなたの大切な人に、
お手紙を書いてみてはいかがでしょうか??
夏休み最後の週末、
図書館へご来館の際は、
ぜひ「昭和の記憶」収集資料展にお立ち寄りください。
スタッフ一同、みなさまのご来場をお待ちしております。
<九華>
「お木曳きで活躍!石取祭の祭車」特集開催中!
2013年8月8日(木)|投稿者:kclスタッフ
8月2日(金)~4日(日)は石取祭が行われていましたね。
ゴンゴンチキチキと鉦や太鼓のにぎやかな音が
図書館にも毎年聞こえてきます。
4階郷土特集コーナーでは9月3日(火)まで
「お木曳きで活躍!石取祭の祭車」
特集展示を行っています。
お木曳きは、20年に一度行われる
伊勢神宮の式年遷宮のために、
御用材を運搬する行事です。
木曽や長野で伐り出された御神木は
桑名を経由して伊勢へと運ばれていきます。
御用材の中でも御神体を入れる容器をつくる
「御樋代木(みひしろぎ)」は特に重要に扱われます。
「御樋代木」が桑名に到着すると
「御樋代木奉迎送祭」が行われ、
石取の祭車も随行して町内をお木曳きして廻ります。
8月30日(金)~9月1日(日)に開催する
桑名市立中央図書館の一大イベント
第8回「昭和の記憶」収集資料展の今年のテーマは
伊勢神宮の式年遷宮と、
桑名のお木曳きについての展示を行います。
お木曳車のミニチュアなど、現物資料も多数展示予定です。
資料展ではこの他にも
石取祭や多度の上げ馬神事などの
桑名で古くから行なわれている神事もご紹介します。
資料展のプログラムも完成しました。
図書館のカウンターなどで配布をしています。
夏休み最後の週末は、
ぜひ「昭和の記憶」収集資料展を見にいらしてください。
ご来場をお待ちしております。
========================
第8回「昭和の記憶」収集資料展
第62回神宮式年遷宮奉祝 受け継がれる桑名の神事
|会期| 8月30日(金)~9月1日(日)
|時間| 10:00~19:00(最終日は18:00まで)
|場所| くわなメディアライヴ1階 多目的ホール
|主催|
桑名市立中央図書館 株式会社図書館流通センター
<いるる>
本だけじゃない!~オンライン(商用)データベースのススメ~
2013年7月30日(火)|投稿者:kclスタッフ
桑名市立中央図書館では、
調べものに役立つツールとして
オンライン(商用)データベース
をご用意しています。
商用データベースとは、
インターネットを使って
有料で提供される
データベースですが、
館内のインターネットコーナーでは、
どなたでも 無料で お使いいただけます。
ご用意しているデータベースは、
事典辞書検索、ビジネス情報や新聞記事の検索、
人物検索など、以下の6種類です。
※新聞記事の掲載範囲はデータベースにより異なります
ので、詳細は図書館へお問い合わせください。
■ジャパンナレッジ
百科事典をはじめとする、日本有数の辞書・事典を
一気に横断検索できるデータベース。
言葉の意味や事柄の基本情報を確認したいときなど、
わたしたちは調べものの最初に使用することが多いです。
詳しくは→ https://japanknowledge.com/
■日経テレコン
日経4紙(日本経済新聞 朝刊・夕刊、日経産業新聞、
日経MJ(流通新聞)、日経地方経済面)やビジネス誌の
最新記事から企業情報まで、幅広い情報を入手できます。
ビジネスや就職活動にご活用いただけるデータベースです。
詳しくは→ http://t21.nikkei.co.jp/
■聞蔵Ⅱビジュアル
朝日新聞オンライン記事検索のデータベース。
1984年8月以降の朝日新聞と『AERA』の記事、
『週間朝日』のニュース面が検索可能です。
朝日新聞の週末別冊版『be』の記事検索もできるので、
「数年前の『be』の特集記事で桑名が紹介されていたのを
見たのだが、その記事をもう一度読みたい…」といった
調べものでは、すぐに対応ができました。
詳しくは→ http://database.asahi.com/library2/
■中日新聞・東京新聞記事検索サービス
中日新聞 朝刊・夕刊、東京新聞 朝刊・夕刊
それぞれの主要記事を蓄積しています。
三重県版、三重県下の全地方版
(北勢、中勢、松阪紀勢、伊勢志摩、伊賀、牟婁)が
収録されているので、
過去のローカルニュースを調べたい時には大活躍!
現在準備を進めている「昭和の記憶」収集資料展の
調べものでは、意外と本では探せなかった
“七里の渡(しちりのわたし)の鳥居の高さ”を
1995年の鳥居建て替えのニュース記事の中から
見つけることができました。
詳しくは→ http://www.chunichi.co.jp/database/
■ヨミダス歴史館
読売新聞の記事検索データベース。
1986年9月以降の新聞記事のほか、
人物データベースや、1989年9月以降の英字新聞
『The Daily Yomiuri』の記事検索もできます。
人気の連載記事は通覧できるように集められているので、
ちょっとログインしてみるだけでも発見があり、オススメです。
詳しくは→ https://database.yomiuri.co.jp/about/rekishikan/about/
■官報情報検索サービス
官報(本紙、号外、政府調達公告版、資料版、目録)を
検索できるデータベース。
データ収録範囲は1947年5月3日から
当日発行分までです。(当日分は午前11時頃に配信)
詳しくは→ https://search.npb.go.jp/kanpou/
以上の6種類のデータベースは、中央図書館4階の
インターネットコーナーで、どなたでも 無料で
ご利用いただけます。
受付時間 : 9:00~20:00 (利用は20:30まで)
1回の利用時間 : 60分 (予約が入らなければ延長可能)
利用をご希望の方は、4階カウンターへお越しください。
また、それぞれのサービス内容、操作方法については、
スタッフまでお気軽にお尋ねください。
データベースを使いこなせれば、調べものや自由研究が
もっとスムーズにできるようになるかもしれません。
<ぐりこ>
「調べる学習相談窓口」のご案内!
2013年7月21日(日)|投稿者:kclスタッフ
青空のまぶしい季節となりました!
今週から、いよいよ夏休みに入りますね。
夏休みといえば、お祭りに出かけたり、
プールに行ったり、宿題に追われたり…!?
小中学生のみなさんも、遊びや部活、勉強など
忙しい毎日を送っているのではないでしょうか。
今回のブログでは、夏休みの宿題にも役立つ
「調べる学習相談窓口」のご案内をいたします!
中央図書館では、7月20日より
「調べる学習相談窓口」
を開設しました。
この夏は、みんなの「なんでだろう?」「不思議だな?」
「知りたい・・!」を図書館で調べてまとめてみませんか?
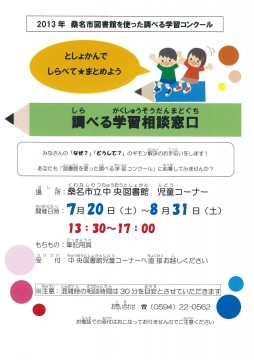
場 所 :桑名市立中央図書館 児童コーナー
開催日時:7月20日(土)~8月31日(土)
13:30~17:00
もちもの:筆記用具
受 付 :中央図書館児童コーナーへ直接お越しください。
内 容 :「桑名市図書館を使った調べる学習コンクール」
作品づくりに関する、個別相談
※注意 :混雑時の相談時間は30分を目安とさせて
いただきます。
調べる学習についてはこちら↓↓をご覧ください。
「これ何だろう?」「どうしてかな?」
身近なことへの疑問、不思議に思ったことを、
図書館にあるたくさんの本を使ったり、実験や観察をしたり、
人に聞いたりしながら調べるのが、調べ学習!
「図書館を使った調べる学習コンクール」に
挑戦してみよう!と思うのだけど、
これからどうやって調べていけばいいのかな?
資料の探し方がわからない・・・などなど。
私たち図書館スタッフが、
調べ学習に取り組むみなさんを応援します!
どうぞお気軽にご来館くださいね♪
たくさんのご参加、お待ちしております。
<九華>