おすすめ本カテゴリの記事一覧
#kclスタッフおすすめ本 『翼を持つ少女』
2022年8月12日(金)|投稿者:kclスタッフ
【 とにかく読んでほしい 】

『翼を持つ少女』
(山本 弘/[著] 東京創元社 2014年刊)
皆様は、ビブリオバトルというものをご存じでしょうか。
ビブリオバトルは知的書評合戦とも呼ばれる、本の紹介コミュニケーションゲームです。
今回紹介させていただく『翼を持つ少女』では、美心国際学園(BIS)高等部へ編入してきた少女・伏木空が、同級生・埋火武人に誘われ、ビブリオバトル部に入部することになります。
空はSF小説が大好きで、面白いSF小説のストーリーの感動や興奮を紹介したい、共感して欲しいと胸に秘めていました。
初めてのビブリオバトルに、自分の好きなSFに興味を持って貰えるのではないかと期待をしながら挑みます。
この作品の中には実際に発行されている本が多く紹介されています。
空が大好きなSF小説の他に、自伝、漫画、雑学書など多種多様な本が登場し、登場人物たちがユーモアを交えながら紹介してくれます。
きっと皆様も、この作品を通して「面白そう!」「読んでみたい!」と思える本と出会うことが出来るのではないでしょうか。
また、この本を読んだ後には、是非、家族や友達と一緒にビブリオバトルを開いて遊んでみてください。
自分の好きな本を紹介することの楽しさや、他の人の発表では、その人の今まで知らなかった一面が見えてくるかもしれません。
~ビブリオバトル公式ルール~
-
発表参加者が読んで面白いと思った本を持って集まる.
-
順番に1人5分間で本を紹介する.
-
それぞれの発表の後に,参加者全員でその発表に関するディスカッションを2〜3分間行う.
-
全ての発表が終了した後に,「どの本が一番読みたくなったか?」を基準とした投票を参加者全員が1人1票で行い,最多票を集めた本をチャンプ本とする.
【参考サイト】
知的書評合戦ビブリオバトル公式サイト
中央図書館でも、10月にビブリオバトルを開催します!
詳細はこちらをご覧ください。
▼本の貸出状況は、こちらから確認いただけます
『翼を持つ少女』
▼出版社
東京創元社
▼書影画像元
版元ドットコム
※次回更新は2022年8月19日(金)の予定です
#kclスタッフおすすめ本 『あさって町のフミオくん』
2022年8月5日(金)|投稿者:kclスタッフ
【 ファンタジー 】
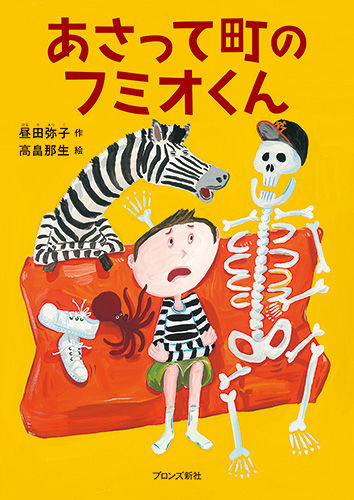
『あさって町のフミオくん』
(昼田 弥子/作,高畠 那生/絵 ブロンズ新社 2018年刊)
この本の舞台は、小学3年生のフミオくんが住む【あさって町】です。
【あさって町】がどんな町かですって?
そこは不思議で、へんてこがあふれている奇妙キテレツな町です。
そんな町に住んでいるフミオくんの日常は、もちろん“普通”とは違います。
ある冬休み、フミオくんは、おばあちゃんの家に泊まりに行きましたが、
「テーブルにひじをつくんじゃないよ」
「おみそしるのネギも残さずたべるんだよ」
「冬休みだからって、だらだらすごしちゃいけないよ」
と毎日、毎日、同じ事ばかり注意されます。
すると、なんとフミオくんの右耳に本物のタコができてしまいます!
これがホントの耳にタコ??
さて、フミオくんの右耳は、タコは、どうなってしまうのでしょうか?
他にも、シマウマに自分の子供だと間違えられたり、ガイコツになったおじさんと町民プールにいったり、学校の帰り道に一足の運動靴から「おいらたちを、はけよ」と声をかけられたり・・・と、へんてこばかり。
お話は全部で4話収録されており、どのお話もクスッと笑え、本を読むのが苦手なお子様にも気軽に読んでいただけます。
ぜひ『あさって町のフミオくん』を読んで、へんてこな日常をお楽しみください。
▼本の貸出状況は、こちらから確認いただけます
『あさって町のフミオくん』
▼出版社
ブロンズ新社
▼書影画像元
版元ドットコム
※次回更新は2022年8月12日(金)の予定です
#kclスタッフおすすめ本 『ロスト・シング』
2022年7月29日(金)|投稿者:kclスタッフ
【 とにかく読んで欲しい 】
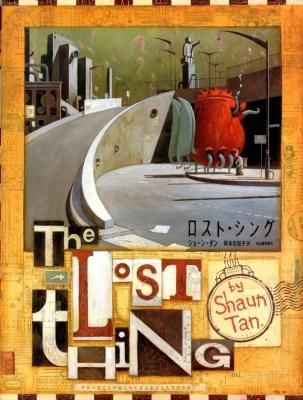
『ロスト・シング』
(ショーン・タン/著,岸本 佐知子/訳 河出書房新社 2012年刊)
思い立って、埃まみれの古びた勉強机の掃除を始めたことがあります。
不用品の山が、机の上やら引出しの奧から出てくる出てくる…
もっとも、当時小学生か中学生か、はたまた高校生か。
その頃の私にとっては忘れ難い思い出の品々だったのでしょう。
プレゼントで貰ったままの包装紙と箱ごと保管してあった時計は、すっかり針を刻むのを止めていました。
そうして忘れ去られていた遺物たちですが、眺めていればおぼろげにでも昔の記憶が蘇ってくるものだなと僅かな感心と懐かしさに浸っていたら、一日が終わっていた経験があります。
『ロスト・シング』
日本語に訳すと「迷子」や「落とし物」「失せもの」といった意味になるそうです。
ショーン・タンの初期作品に連なるこの代表的な絵本は、タン自身の手で映像化もされており、短編アニメーションとしても評価の高い大人絵本となっています。
そのタイトルの通り、奇妙な形をした「迷子」が、失ってしまった居場所を探すお話です。
主人公の少年と「迷子」は居場所を探して街中を徘徊しますが、忙しい大人の目に迷子の存在は映りません。
私の勉強机のように、形の残る思い出の品や記憶の奧深くに仕舞い込んでしまった大切な思い出と同じで、見えなければ無いのと同じ…
見えなくてもいい存在に気を留めない大人たちの様子に、チクッと刺さる何かがあります。
そんな何かを忘れてしまった大人たちへ向けた本書は、懐かしくもどこかディストピア感溢れる魅力を秘めています。
徐々に落とす側の大人になっていく自分と、忘れられたものたちの行方。はたしてこの両者は誰の物語なのでしょうか。
読後の余韻まで楽しんでいただける作品です。
▼本の貸出状況は、こちらから確認いただけます
『ロスト・シング』
▼出版社
河出書房新社
▼書影画像元
版元ドットコム
※次回更新は2022年8月5日(金)の予定です
#kclスタッフおすすめ本 『キノの旅 the Beautiful World』
2022年7月15日(金)|投稿者:kclスタッフ
【 ファンタジー 】
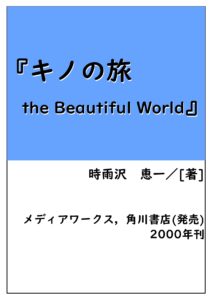
『キノの旅 the Beautiful World』
(時雨沢 恵一/[著] メディアワークス,角川書店(発売) 2000年刊)
『キノの旅』は、主人公キノがしゃべるモトラド(※二輪車。空を飛ばないものだけを差す)に乗って旅をしている物語です。
多くは辿り着いた国での出来事がメインで、それに合わせてタイトルも「~の国」となっています。
ただ、どこの国も何かしら問題を抱えており、その極端な振りきれっぷりから、タイトルからどんな内容だろうと推測するのも個人的な楽しみです。
たとえば、一話のタイトルは「人の痛みが分かる国」です。
この国はとても技術が進歩しており、あらゆる事を機械が担っています。
ですが、きれいに整えられた町に人影はありません。
それどころか、面積の半分以上を占める居住区で、遠く距離を取って建てられた家に一人で住み、誰かと交流することもなく暮らしているようでした。
さて、ここでタイトルです。
“人の痛みが分かる”から、この国の人々はこんな生活をしているのですが、では何故そうなってしまったのでしょう?
シリーズは年に一冊程のペースで刊行され、その度にイラストを描かれている黒星紅白さんの画風が変わっていくのも楽しみになっています。
そして一話完結の短編集となっており、繋がりはありますが、どの巻、どの話からでも読み始められるので、好きな画風の巻から手に取ってもよいのでないかと思います。
「世界は美しくなんかない、そしてそれ故に美しい」
そんな『キノの旅』の世界を楽しんでくださったら幸いです。
▼本の貸出状況は、こちらから確認いただけます
▼出版社
※次回更新は2022年7月29日(金)の予定です
#kclスタッフおすすめ本 『はじめてであう小児科の本』
2022年7月1日(金)|投稿者:kclスタッフ
【 子育てに悩む人へ 】
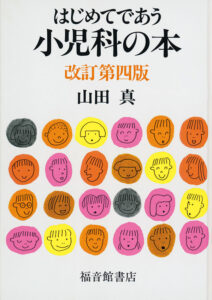
『はじめてであう小児科の本 改訂第4版』
(山田 真/著 福音館書店 2016年刊)
子育てで困る事と言えば、やはり「病気」です。
はじめて子供が熱を出した時のあの不安感…
しっかりと意思の疎通ができない乳幼児期は、特にどうしてよいのかわかりません。
みんながそうなのか?この子だけなのか?
受診しても、「ちょっとした気になること」は、なかなか先生に聞くことができず、精神的に参ってしまうこともありました。
そんな時期に、この本を読んで何度か助けてもらいました。
目次を見てもわかるように、病気の種類ごとに細かく分けてあり、症状や特徴、治療方法が書いてあります。
著者は小児科医の先生なので、実際に、受診した人の状況なども合わせて書いてあり、自分と重ねることができて、ちょっと安心します。
例えば同じ下痢でも、軽い場合と重い場合どのような違いがあるのか?何に気を付けたら良いのか?
情報過多の時代、安易な自己判断は怖いですが、自分自身の精神安定剤として、軽い気持ちで、読んでみてはいかかでしょうか?
▼本の貸出状況は、こちらから確認いただけます
▼出版社/書影画像元
※次回更新は2022年7月15日(金)の予定です



